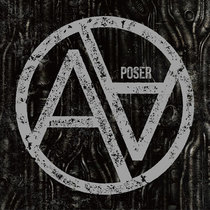INTERVIEW
AA=
2013.11.20UPDATE
2013年12月号掲載
Member:上田剛士 (Ba/Vo/Prog)
Interviewer:吉羽 さおり
AA=の4thアルバム『♯4』は、『♯』と『4』によるスプリット・アルバムとなった。『♯』は、AA=、上田剛士がキャリアのなかで研磨してきたエレクトロニックなアプローチの作品。攻撃的かつ、エレガントな鋭さや物語性も湛えた『♯』に対し、続く『4』はバンド・サウンドが主体で、衝動が生むメロディが輝く作品となった。一見別のバンドの作品の佇まいだが、異なる角度からAA=の中核へと掘り進んでいくようなスリリングな内容だ。
-4作目のアルバム『♯4』は、『♯』と『4』の2作連続のリリースとなりました。それぞれ特徴を持った作品ですが、今回2作に分けたのはどういったことからだったのですか。
話のきっかけとしては、AA=としてこれまで3枚アルバムを作って4枚目を作るときに、今までとはちがうというか、違った試みをしたいなというのがあったんですね。自分が制作に向かう姿勢として、新鮮であるということを求めたのがきっかけで。どういう形がいいのか、いろいろ考えている間に段々と2枚に分かれて。自分の音楽の幅の両極端じゃないけど、それをぱっつり2つに分けたらどういうものになるんだろうっていうのが最初です。
-それが、エレクトロに特化したものと、バンド・サウンドに特化したものの2作で。
結果、そういう感じになったというか。当たり前のようにそういうふうになっていったというか。
-曲作りの段階でも分けて行なっていたんですか。
最初は全然ですね。最初は割といつもどおりに作りながら、どういうのがありかなって思っていたんです。最初は2つに分けるというよりは、どっちかに偏ったもの、特化したものを作るのはどうかってなっていうのがあって。それを作っていくうちに、そうなるとやっぱり反対側も必要だなってなってくるというか。それで結果、2枚になって。エレクトリックなものがメインになっている、通常自分がAA=となってからもそうですけど、その前のバンドのときから自分が探し続けている、作り続けているスタイルの延長線上にあるものと、もう一方はもっとシンプルでエモーショナルで。メロディがシンプルに聴けるようなものっていうのが、なんとなく分かれているという感じですね。
-バンド・サウンドがメインの『4』は、バンドらしいソリッドな仕上がりで、それがAA=としては新鮮であり面白いなと思ったんですが。制作のプロセスとして、これまでとちがう曲作りやサウンド作り、アレンジの方法もありましたか。
曲作りとしてはとくに変化はないんだけど。どっちかっていうと引き算で、今までだったらそれにもうちょっとちがう要素を入れたくなって入れていたのが、今回は入れない、我慢してみようみたいな感じでやっていって。それでも自分らしくある、自分のものとして完成したものが残ったという感じですね。
-我慢、なんですね(笑)。
そうですね。どうしても、頭のなかに浮かんじゃうと入れないわけにはいかないので。だから、作っていて頭のなかにそういうものが浮かんじゃった曲に関しては外しちゃうというか。
-デモの段階から実際にレコーディングなどでメンバーに託していく部分ではどうですか。
普段は、デモをみんなに聴かせて、各自のニュアンスやプレイのアイディアをどんどん入れていってもらうんだけど。今回いちばん違ったのは、デモの段階でもみんなで1回合わせて、曲をもんでいるんですね。これは普通のバンドだと当たり前なんだけど、AA=というバンドのスタイルでは、今までレコーディングに入る前にみんなでその曲を合わせるということはなくて。レコーディングのときに、自分が作ったデモからメンバーひとりひとりの音に入れ替えていくというか、レコーディングでメンバーひとりひとりが自分のアイディアを入れていって、それを最終的に作り上げていくというスタイルをずっとやってきていたんです。だから、実際にメンバーが揃ってその曲を演奏するのは、レコーディングが終わった後のライヴのリハでというのがずっと自分たちのスタイルだったんですね。今回は、ちょっとその前にスタジオに入ってみようかって言って、みんなでスタジオに入って曲をやってみるっていう。すごく当たり前のことをやってみたっていう(笑)。それも今までやってないことっていうのを求めていたので。
-全員で、面と向かって曲を作っていくのは、感覚的にも結構違いますよね。
違いますね、やっぱり。そのたびに、各自が反応し合って作り上がっていくので、いわゆるバンドらしくなっていくというか。
-今までその“バンドらしい作り方”をしてこなかったのは。
それが面白いから。やってみたいからっていうのがいちばんの理由でしたね。それぞれが自分のパートを作り上げて、それを組み上げていくっていう。通常だったらやらない形なんだけど、うちらはそれができるので。それで一体どうやって作品を作り上げることができるんだっていう、実験をしている感じですよね。たとえば、これまでのアルバムでも、とにかくメンバー同士が全然会わないとか、なるべく会わないようにして作ろうってやったりもしたんですよね(笑)。ミックス作業も、エンジニアの人と会わないでやろうっていうことでインターネットを通してそれでやったりとか。ほんと、実験ですよね。そんな感じで、レコーディングできるのか?っていう。それが意外とできたりしたので、それが元になって、自分らのレコーディングではそのスタイルがずっとあったんですけど。