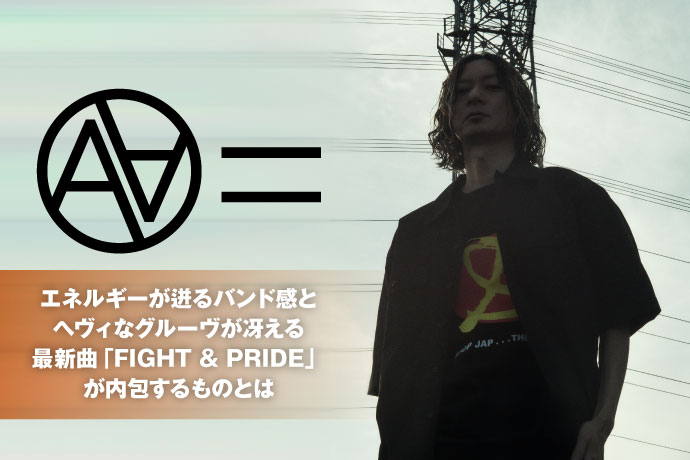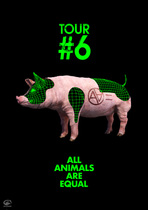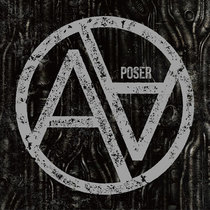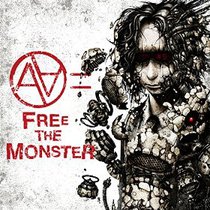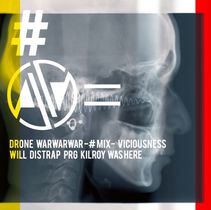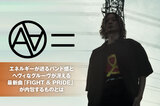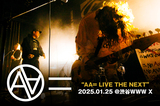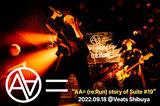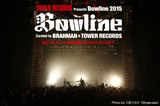INTERVIEW
AA=
2024.05.30UPDATE
2024年06月号掲載
Member:上田 剛士(Ba/Vo/Prog)
Interviewer:吉羽 さおり
AA=名義としては、2021年のコンセプチュアル・アルバム『story of Suite #19』以来、約2年半ぶりとなるオリジナル音源『FIGHT & PRIDE』。収録曲である「FIGHT & PRIDE」、「CRY BOY」はそれぞれ、世界一斉公開となったNetflixシリーズのアニメ"餓狼伝: The Way of the Lone Wolf"のオープニング主題歌、エンディング主題歌として書き下ろされた。「FIGHT & PRIDE」はAA=の動の部分と言えるアグレッシヴさで、曲も歌詞も重厚に描かれた曲であり、「CRY BOY」は静の部分。美しいメロディ・ラインで繊細に語り掛ける、表情豊かな曲だ。今回のアニメ作品では上田剛士名義で劇中音楽も担当しており、作品の音楽を一手に担う形となった。作品への携わり方や、オープニング主題歌、エンディング主題歌それぞれについて話を訊いた。
-デジタル・シングル『FIGHT & PRIDE』がリリースとなりましたが、今回収録の2曲「FIGHT & PRIDE」、「CRY BOY」はNetflixシリーズのアニメ"餓狼伝: The Way of the Lone Wolf"のオープニング主題歌、エンディング主題歌となっています。このアニメでは劇中音楽も担当されているということで、作品全体に関わっているようですね。
今回は、もともとは劇中音楽の話があって、そこからオープニング主題歌/エンディング主題歌へと広がった感じだったんです。"餓狼伝: The Way of the Lone Wolf"の碇谷 敦監督とは、監督が以前手掛けたアニメ"錆喰いビスコ"で音楽をやったことがあって、その流れでいただいた話だったんですけど。前回の劇中音楽はちょっとロックっぽいものというか、バンドっぽいサウンドが多く入ったものが監督のイメージだったようで、それでオファーをいただいたもので、そのときの感じがやりやすく思ってくれたのが今回の話にも繋がったのかなと。
-劇中音楽となると、オープニング、エンディングとはまた違った作り方となりますか。
監督や制作のスタッフの方といろいろ話をしながらという感じですね。お題というか、こんなシーンに合う曲をみたいなことが多いので、それをイメージしてひとつひとつ作っていく感じです。
-劇中音楽は劇中音楽で、また面白さがありそうですね。
それはすごくありますね。普段自分が作っているものとは全然違う方法というか、基本的に自分が作るものは、音が主役で中心になりますけど、劇中音楽に関しては絵であったりストーリーであったりに色づけするものって立ち位置になるので、その意味では、同じ音作りでも全然違います。
-絵やストーリーにはめていくということでは、音にしても、曲にしてもより実験的にできる部分もありそうですね。
実験的なこともやりますね。それで先方に投げてみて、気に入られるかどうかというのはありますけど。あとは劇中音楽の場合はストーリーの邪魔にならないようにということも大事なので、そこも気にしたりはしていますね。
-主題歌もその流れからだったということですが、オープニング主題歌、エンディング主題歌それぞれで監督や制作からのオーダーはありましたか。
エンディング主題歌に関してはいくつかあったので、その希望を聞いたものにしていますね。オープニング主題歌については任せてもらえたので、せっかくこうしてトータルで携わることになったし、劇中音楽を作っているなかで候補としてあった曲やフレーズをもとにして、曲を作り上げていきました。
-特にオープニング主題歌となる「FIGHT & PRIDE」はかなり生々しく、バンド・サウンドの荒々しい手触りのある音になっていますね。
そうですね、同期モノという意味ではそんなに多くないです。わりとシンプルになっていて。
-そういうところも上田さん自身でイメージしたものがあったんですか。
そこは結構、マイブーム的なところかもしれないですね(笑)。
-そうだったんですね。アニメ作品が格闘モノということで、人と人がぶつかり合う、生々しさもあったのかなと思っていました。
それは単純に劇中音楽を作っている際のひとつのテーマでもあったので。アニメの影響やストーリーの影響みたいなものは、最初の時点からありました。アニメ自体がかなりちゃんとした格闘モノで。
-格闘シーンは、実際の格闘家の方の動きを撮影してアニメに描き起こすというリアルなものになっているそうですね。「FIGHT & PRIDE」はそういう格闘シーンの臨場感にもハマります。またサウンドの雰囲気として感じたのが、90年代の、例えばANTHRAXとPUBLIC ENEMYの「Bring The Noise」ではないですが、メタルとヒップホップなど、強力なもの同士がタッグを組んでいった時代のような匂いも感じました。
それは自分的には意識しているところかもしれないですね。自分のルーツや歴史的なところでもありますし、中心にあるもので、それを久々に今の自分の空気感でやってみるというのはあると思います。これは今回の曲だけに限らずで、どのくらい形になるかはわからないですけど、そのひとつではあるんじゃないかなと。
-その巡りが、今来ているのはなぜなんでしょう。
これは、なんとなくですかね。
-昨年は、ご自身の名義で初のカバー・アルバム『TEENAGE DREAMS』をリリースして、音楽的なルーツを振り返ることもあったと思いますが、何か影響するものはありましたか。
そういうのもあるのかもしれないし、でも特にこれだっていう理由もないんです。突然変わっちゃうかもしれないですし、わからないんですね(笑)。常に変化してくことは目指したいし、今の自分のリアルなものは常に作っていたいんだけど、なんとなくそのときの空気感みたいなもので、今やってみるのが面白いかなと思います。