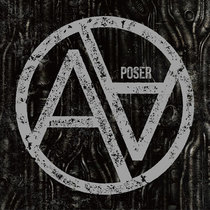INTERVIEW
AA=
2024.05.30UPDATE
2024年06月号掲載
Member:上田 剛士(Ba/Vo/Prog)
Interviewer:吉羽 さおり
戦っていたくて戦っているわけじゃないということが、世の中には多くある
-「FIGHT & PRIDE」でのザラザラとした肌触りやアグレッシヴさは新鮮でした。そういう音の質感も大事に作っているんですか。
そういうヘヴィさや音については、作っているときに曲自体が求めている感じがありましたね。
-ギターのリフはもちろん、ビートも頭からガツンとしたインパクトがありますね。
良かったです。グルーヴに関しては、ドラムのYOUTH-K!!!(ex-BATCAVE)と結構話しましたね。さっきおっしゃっていたような90年代くらいからのラウドロックって、ヒップホップの影響が強いじゃないですか。なのでビートが大きかったり、強かったりするんですよね。そのあたりは自分の中にも自然と根づいている感じです。当時はクロスオーバーの時代で、いろんな要素やジャンルをぶつけ合って、そこで新しいものが生まれていく時代で。今ではいろんなものがミックスされた音楽が普通で基盤となっていますけど、その時代のものはよりシンプルに組み合わさっているので、今聴いても強いんですよね。
-そうしたグルーヴやバンド感を生むレコーディングはどのような感じでしたか。
基本はひとりひとりで録っているんですけど、その場で一緒にやっている感じですね。結局そういう録り方をしないと、その感じにならないのかもしれないです。コンピューターが中心となる以前は──その当時もひとりひとりでは録っているんですけど、基本的にはその場でみんなで一緒に演奏をしているので、グルーヴが生まれる。今の時代は、レコーディングや、音楽を作ることがより個人的になって、自由にいろいろやれるようにはなっているんですけど、以前の方法で良かったものは、俺らみたいなバンドは忘れないでいるほうがいいかなとは思っていますね。新しい世代は新しいものをどんどん作っていっていいんですけど。そういう意味ではこの感じを新鮮に思ってくれる人もいるかもしれないですしね。
-歌詞についてはいかがでしょうか。「FIGHT & PRIDE」では1語が持つインパクトがより強いものになっています。
作品自体が、戦いがテーマとなっているので自然とそういうふうになっていますね。一昨年や昨年くらいに作っているんですけど、そのときの自分の思う戦いが基本的にはテーマとなっているので。それは社会情勢とか、そういうものも含めてなんですけど。
-社会情勢ということでは、この数年でさらに世界中がヒリヒリとした状況が続いていますしね。
ちょうどこの曲を作っていたときくらいに、ロシアによるウクライナ侵攻が始まったりもしていたんです。ただ戦いというのは描くのが難しいところもあって。
-どの側面で描くかという。
決して戦っていたくて戦っているわけじゃないということが、世の中には多くあるじゃないですか。どちらかというとそういうほうが、自分としては引っ掛かるんですよね。そういう状況にしているやつらは戦っていなかったりするし──これは戦争みたいなものに限らずですけど、世の中ってそういうものだよねみたいな。自分たちの身の回りにおいても、多いじゃないですか。
-上が決めたことに巻き込まれていくようなことが、往々にしてありますね。
そういうところでいろんな歪みが生まれてくるし、悲しい話が生まれてくる。いらない確執や分断が生まれてくるものなんです。その究極が、リアルな戦いの場で。決して他人事ではないなというのはつくづく感じていますね。
-それが凄まじいうねりのあるサウンドからで炙り出される感じが曲にはある。さらにエンディング主題歌「CRY BOY」は、より人間の心の内側に迫っている曲です。
そうですね。自分としては、「FIGHT & PRIDE」と表裏一体でテーマは同じなんです。エンディング主題歌に関しては曲調や、こんなイメージでとは監督から言われていて、その通りになったかどうかはわからないんですけど、いくつか提案したなかで、監督がこの方向がいいということで作っていったんですよ。なので、より「CRY BOY」はアニメに近いかもしれないですね。エンディングとしてこんな世界観がほしいってところから広げていって、そこにAA=としてのアイデンティティや、バンドとしてどう表現するかが加わっていくと。
-アコースティックなアルペジオでの始まりから、静かに心に問うように、また感情の流れに沿って曲が紡がれていくイメージがあります。
自分としてもそういうつもりでもありました。あとは、余韻が欲しい感じでは作っていますね。エンディング主題歌という、ひとつの物語の最後に来る曲でもあるし。今回は、オープニング主題歌「FIGHT & PRIDE」の頭から、エンディング主題歌「CRY BOY」の最後まででひとつの作品になりうるといいなという思いは、自分ではありましたね。なかなかひとつの作品で、オープニング主題歌もエンディング主題歌も劇中音楽もと携わることはないので、そういう意味では、普段のタイアップ曲とはまた違う、トータルでの作品性が作りやすいところはありました。なので、すごく面白い制作になりましたね。
-ここまで作品に寄り添って作っていくというのは、今までないことですか。
ないですね。映画やアニメで劇伴をやらせてもらうことは何度かありましたし、オープニング曲やエンディング曲をそれぞれ書くことはあったんですけど、ここまでというのはないです。
-今回それをやってみようとなったのは何が大きかったですか。
決めてくれたのは、監督とスタッフのみなさんですけど、そう言われて断る理由は何もないなっていうか。こんな面白いチャンスないじゃないですか。劇中音楽だけでも十分面白いのに。
-劇中音楽、オープニング、エンディングと手掛けるとなるとこの制作にかかりきりになる感じですか。
一昨年はほぼこの作品に時間を使っていましたね。コロナ禍ということもあったので、よりじっくりと向き合うことができましたけど、基本的にスタジオにこもって作業をしているのが好きなんですよ。それが性に合っているので、全然苦ではないんですよね。
-ここ何回かのインタビューでもずっと制作をしているというお話がありましたが、この作品のことだったんですね。
ポロポロと言っていたかもしれないですね(笑)。
-劇中音楽のような普段とは違うクリエーションから、AA=に還元されていくことはありますか。
制作面ではいろいろありますね。普段使っていない機材を使ったり、普段はやっていないような制作の仕方をしてみたり、楽器構成から全然違うときもあるので、それを機に機材を増やしてみたりとかもあるし。ただそのなかでバンドのほうに還元されるのは、ごくわずかなんですけど、エンジニア的な部分はわりと変わったりしますね。どうしてもレコーディングを自分でやることになるので、何十曲もレコーディングしていくなかで、違うこともやってみたくなるし、という。
-今回は作品あっての曲でもありましたが、次にどういう曲が出てくるのかが楽しみにもなります。制作はずっと続いているものと思いますが、今はどのような感じですか。
今は自分のものを作るタームに入ってきている感じですね。前回のアルバム『story of Suite #19』はコンセプチュアルで、それまでとはテーマが違う作品で、今回はアニメという作品をもとにして作ったものだったので、今はまた新たなスイッチで、作っていて楽しいです。