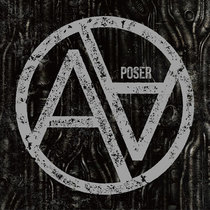INTERVIEW
AA=
2021.11.30UPDATE
2021年12月号掲載
Member:上田 剛士(Ba/Vo/Prog)
Interviewer:吉羽 さおり
AA=の最新アルバム『story of Suite #19』は、これまでのアルバムとは佇まいが違う、コンセプチュアルなアルバムになった。昨年10月に行った配信ライヴの映像作品『DISTORT YOUR HOME』にコンパイルした、スペシャルCDシングル「Suite #19」をもとに物語を紡ぎあげた今作は、そこから浮かび上がる映像に音を重ね合わせるように曲が進んでいく。静かな語りから始まって、引き込まれるようにこの物語に没入する、新たな味わいがある作品だ。コロナ禍という未曾有の出来事が、この作品を生んだのは間違いない。とはいえ、そこにはただリアルなもの、リアルな叫びが映し出されるのでなく、寓話的な余韻を聴き手に与えてくれる。ここから何を拾い、自分と重ね合わせるのか。また時が経ったときに、この音楽がどう響くのか。そうした音楽的な楽しみというものが詰まったアルバムだ。
-今回のアルバムは、シングルとして発表された「Suite #19」をもとにしたストーリーだとうかがっています。
昨年行った配信ライヴ"DISTORT YOUR HOME"をパッケージ化するときに、せっかくだから新たに何かつけようということになって作ったのが、組曲となったシングル「Suite #19」だったんです。
-制作自体はこのコロナ禍でも変わらずに続けていたんですか?
そうですね。外注の仕事や別のプロジェクト的なものがあったので、ライヴをやらないということ以外は、特に変わらずでいましたね。
-制作する、作品を作るということに関して、ライヴがないという状況が何か影響はしましたか?
やっぱり、バンドとしてはライヴがないというのは大きいですよね。しかもそれが外的な要因でできない、自分だけではなくてみんなができないという状況は、誰もが想像していなかったことで、数ヶ月の間に突然そうなってしまったので。
-わずかな時間で、生活のスタイルなどいろんなことが劇的に変わりましたね。そういった2020年~2021年の状況が今回のアルバムの中に練りこまれているのを感じます。
制作の過程において一番大きく違うのは、ライヴをやるとなるとライヴハウス、フロアもウワーッと熱気があってもみくちゃになるじゃないですか。それで自分のバンド生活というか、バンドとしてのアイデンティティができあがってきたなかで、それができない、まったく違う状況になってしまったのは初めてのことだったので。自分が曲を作るとなったときにも、今まではライヴの状況をイメージして作っていたものが、それがイメージできないというか、イメージすると嘘になってしまう、リアリティがなくなってしまうんですよね。ライヴをイメージしないで作品を作るのは、初の体験でした。
-ライヴを想定しない曲作りをどうしていくのかという部分で試行錯誤はありましたか? 曲作りの第一歩として、上田さんはどう考えていましたか?
結果的には、今自分が作るべきものは何か、作りたいものは何かというすごく単純なところに落ち着くんです。とにかく嘘がなくて、今の自分の状況とか気持ちとか環境の中で、作るべきものは何かという感じでしたかね。
-それが最初のシングルとして出たものですね。
そうですね。それがもやっとだけどあって形にできたのが、ライヴ作品に同封した組曲、3曲でひとつのものになったシングルだったんです。
-その時点では、そこから続くアルバムへの道筋というのはあったんですか?
その時点では何もなかったですね。そのときは、とりあえず今作れるものとか、作りたいものってなんだろうと考えて辿り着いたものだったので。それを作り終えてみて、もっとこれを掘り下げたいなというか、まだ足りないなというのが自分の中であったんです。そう思って、あと2、3曲足したいなというところから始まって。なのでアルバムということは特に意識せず、シングルが限定みたいな形で出していたので、また違う形で作品にすることができるかもなとは思いましたね。それで、あまり深く考えずに作り始めていて。足りないもの、足していきたいものをどんどん作っていったら、最終的にはアルバム・サイズになっちゃったという。
-そうだったんですね。それくらいまだ言い足りないものがあったというか。
描き足りないという感じでしたね。まだまだ。自分の中で、これで完成みたいな形にはなっていなかったので、思ったよりも曲が必要だったんだなと思いました。
-シングルを制作していた昨年から、また時間が経つにつれて状況が一進一退して、刻々と変わっていくような感じもありました。
そうですね。昨年配信ライヴをやったり、シングルを作っていたりした時期が一番、この先が見えない感じだったんじゃないかなと思います。バンドマンとしてという以前に、社会的な状況として、まだいろんなものができていなかったり、足りなかったりもしてみんなイライラして、ギスギスしていて。
-そうしたままならないフラストレーションも、このアルバムの物語として映り込んでいます。
今の状況を何か"メッセージ"として音にしようということでは全然なかったんですけど、自分が作るものには当たり前に今の状況が影響されるし。それを表現するとなったときに、ある意味こうして別の視点から見るような形で表現するのが、自分にとっては一番やりやすかったというか。しっくりきたということですかね。
-物語のイメージとしては、ある国に冬がやってくる。その間はこの国の扉を閉めて、長い冬をしのいでいく。その閉鎖された空間の中で、様々な感情が渦巻いたり、起こったりするというストーリーですね。
そうですね。
-そこで最後に、春がやってくるのかどうか、そうした希望がひと筋見えてくるのはいいなと感じました。
そこは自分の中の落としどころというか、物語の終わりとしては必要だったというか。そういうものを作りたかったですね。
-ただそれが、単純に春がきて良かったねという明るいものでないのがいいなとも思いました。終曲「Chapter 9_SPRING HAS COME、取っ手のない扉が見る夢、またはその逆の世界」での、"前と同じ春はない"という表現がとても重みあるものだなと改めて感じます。
実際にそうだと思いますしね。自分たちがこの約2年の経験をしたかしないかで、迎える未来は全然違うし、そのなかでも変わらない自分たちの希望や求めるものとか、やりたいこともあるし、そういったものを表現しておくべきかなとは考えました。
-上田さん自身、この2年間での変化はありますか? 振り返ってみて、そういえばこれは変わっていたなと思うところとか。
やっぱり、この2年間でライヴができなくなったことは大きかったですね。ラウドなバンドはみんなそうだと思うけど、自分たちがずっとアイデンティティとして作りあげてきた、カオスな状況のライヴとかが全面的にダメで。今まではダメって言われても、"関係ねぇだろ、何言ってんの"ということだったけれど、今回は自分たちもダメな理由がよくわかっている。そういうことは今まで頭になかったものだったので、大きかったですよね。混乱もするし、自分がやってきたことの全否定じゃないけど、そういうのを認めざるを得ない部分もあるというか。ただ、また今までのようなライヴができる世界が戻ってきたときに、この経験をしているのとしていないのでは感じ方などが違うだろうなとも思うし。
-そうですね。
自分の音楽的には、今回はこの作品を作ったり配信ライヴをやったりしたことで、今まで思ってもみなかった視点で物事が見られた。バンドに関しても音楽に関しても表現に関しても、そういうものができたのはすごくいい経験になったと思います。AA=になってからアルバムには番号をずっと冠していたんですけど、今回初めてタイトルを付けて。次のアルバムでまた番号に戻るかどうかわからないですけど、戻ったとしても、この経験を経てのものになるのは間違いないので、それは、ちょっと楽しみでもあるんですよね。自分がまた物事を違った目線で見られるようになったという意味では、成長かもしれないし、気づかされたこともあったので、決してネガティヴな面だけではなかったなと思います。
-まさにこの時期があったからこそ、できた作品ですね。
そうですね。逆に言えば、表現方法からして、これがなかったらできていないと言い切れるくらいの作品です。
-配信ライヴのような"見せる"ことに特化したライヴには、どんな体感がありましたか?
面白かったですね。通常のライヴとは全然違うので、ライヴと言いながら映像作品のニュアンスも強いし、観る側の目線をこちら側が決めちゃうというものでもある。それによって、音を映像としてさらにコントロールできるので、まったく別の表現方法としては面白かったですね。
-AA=のアンサンブルの勢いとか、深みとか、もともとのライヴでもそれぞれのプレイヤーの見どころがものすごくあるから、そういう意味では映像映えもするかなとは思いましたね。
映像にするっていうのはなかなか難しかったですけどね(笑)。自分的にどういうものが正解なのかわからないし。