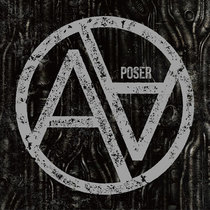INTERVIEW
AA=
2013.11.20UPDATE
2013年12月号掲載
Member:上田剛士 (Ba/Vo/Prog)
Interviewer:吉羽 さおり
-その方法だと、ある種設計図通りにも仕上がるということですよね。
そうですね。
-今回のようにバンドで作るとなると、それが通用しない部分もありますね。
うん、その前に1回みんなで壊しちゃうというかね。それが当たり前に面白くもあるので。バンドの醍醐味じゃないけど。そういう意味では肉体的かな、今回は。今までは頭で考えて作っている部分が多いけど、もうちょっと有機的というか。それは、とくに『4』側のバンド・サウンドを重視するアプローチだったから必要になったのかもしれないし、そんなメンタルだからそういう作品ができたのかもしれないし。
-なるほど。改めてまず4人で合わせてみようとなった時のムードはどういう感じだったんですか。
でもね、普段だったらライヴの前にやってる雰囲気がそのままレコーディングになるだけなので。この形でレコーディングできるんだっていうのがあるから、みんなにとっては普通に面白かったんじゃないかな。今までのほうが不安というか(笑)。
-ああ、そうかもしれませんね。
非常にそれはいい感じでしたね、やっていて楽しいというか。アレンジをああしようこうしようっていうのが、その場でいろいろとできるから。BPMからみんなで考えてみたりとか。曲の尺とか展開も変えてみたりとか。誰かがやったフレーズに反応することで曲が変わったりもするし。久々に面白いです、それは。
-バンドだったらやってくることを、一度封印していたんですもんね。
それまで自分自身が長い間ずっとバンドをやっていたので。もともとAA=を始めたときに、そういう実験をしたいっていうのがあったんです。
-これまでの作品での実験を経て、今回のようなバンドらしい作り方をしたことでの発見はありましたか。
もちろん、今回の作り方は、今回の作品には非常に合っていて正解なんだけど、でもそうじゃない今までの形も実は面白くて。そのときそのときの自分のメンタルとか、バンドの求める感じとか、そのときの気分でできればいいなと思っているんですよね。これからもっと違う方法をやりたくなるのかもしれないし。そういうことをできるスキルを持っている連中が集まっているので。普通じゃない感じがいいんだよ、っていう感じでね。そういう意味では今回、普通にやることが自分らにとっては普通じゃないことで面白かったんですよね。ただこれが、毎回やるかっていうとそれはわからないっていう感じですね。
-なるほど。では、歌詞はどんなふうに作っていったんですか。
歌詞もそういう意味では、自分のところは自分で作るし、TAKA(TAKAYOSHI SHIRAKAWA)の部分はTAKAにそのまま投げちゃうっていう感じですね。自分が作った歌詞の部分をTAKAが見てそれに応える感じで作る時もあるし、自分がテーマを最初に考えてそれを投げてTAKAから作ってくるというのもあるし。テーマはなんとなく自分が指さして、こっちの方向くらいのところは投げていますね。それ以降はお任せというか。
-2枚それぞれのテーマでは、いかがですか。『♯』は音的にも硬質で、歌詞の世界も乗り越えていくイメージで、『4』はより肉体的で高揚感のある内容だなとも思います。
自分のなかでのなんとなくの方向性としては『♯』のほうは未来を意識していて。それは必ずしも美しい、きれいな未来ということではなくて、問題や疑問であったり、うっ屈したものを含む未来。これから起こる、考えられるようなものを含んだ未来、よりリアルな未来みたいなものがテーマとしてあって。『4』は、どっちかというとそれとは逆に過去というか。自分自身のエモーショナルなもの――今まで自分が考えてきたものや、それを経て思うことであったり、記憶みたいなものであったり、そういうことを思い起こして、見つめ直しているというのが、大まかなテーマのちがいですね。
-それぞれの作品を1曲ずつお聞きしていきたいのですが、まずは『♯』の1曲目となる「DRONE」。この曲は幕開けに相応しい、ピアノの旋律で物語的にはじまっていく曲で。ポエトリーでありながらも重いものを含んでもいる曲ですね。
そうですね。もともと『♯』と『4』で分けるアイディアがはっきりと指針として見えたのが、デジタル・シングルに入った「WARWARWAR」と「HUMANITY2」の2曲なんですけど。そうやって「WARAWARWAR」側の曲を作っている世界観のなかで、ちょっと自分のなかではちがうテンションの時にできた曲で。わりとこの曲は、一瞬にしてすぐにできたんですよね。
-言葉や音がそのまま絵として浮かぶような曲ですよね。
流れや世界観も含めて、自分のなかでも入り込んで作れたので。そういう意味では、特別な瞬間にできた曲なんだけど。1曲目がいいんじゃないかっていうのは、メンバーからの意見だったんですよね。自分のなかではそういう意識は全然なく、アルバムに入れるかどうかもわからないくらいで作っていて。そういう意見が出たときに、ああその通りだなって思って。それでこっち側、『♯』の世界がきちんと見えた感じなんですね。