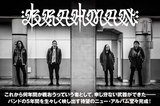LIVE REPORT
BRAHMAN
2022.01.13 @中野サンプラザ
Writer 石角 友香 Photo by 三吉ツカサ (Showcase)
『Slow Dance』リリース時のインタビュー(※2021年9月号掲載)でTOSHI-LOW(Vo)は、コロナ禍において観客に行動の制限があるなかで、以前と同じようなライヴを行うことへの違和感を話していた。そしてその違和感の壁を超えるライヴのあり方は、単にバンドの静の部分を抽出したセットリストや、映像、演出を押し出すという手法そのものでもなかった。それらは重要ではあるが、あくまでも要素だ。そのことが前回、映像化もされたツアーからより前進した今回の"BRAHMAN Tour -slow DANCE HALL-"で、証明されたのではないだろうか。BRAHMANらしいニュー・スタンダードであり、且つ他のあらゆるアーティストにも影響を与えるアティテュードでもあったのだから。本稿ではツアー追加公演の中野サンプラザ2日目をレポートする。
まず目に飛び込んでくるのはドレープ幕に囲まれ、紗幕に覆われたステージ。一気にいい緊張感が全身に走る。ほぼ漆黒と呼んでいい暗転と同時にさざなみのような拍手が起こり、紗幕には震える"霹靂"の文字。土砂降りの雨や雷の映像は、温度が感じられるほどリアルだ。ホールのどの場所から見るかによってバンドの生々しさは違って感じられると想像するが、少なくとも2階席からのそれは、生身の人間の存在を声や楽器の音色で表現することであり、荒天の中、演奏するという"架空"がむしろ音楽を鮮明に響かせる。そのあと、ブルガリア民謡の「お母さん、お願い」が廃墟やビル群が高速で編集された壮絶な映像を伴い流れ、ツアー・タイトルが投影されたときの鬼気迫る体感は稀有なものだった。
 「空谷の跫音」、「Oneness」、「俤」などが、バンドという生き物の細胞や組成が変化してきたことがわかる現在の演奏で、時代を超えて刻み込まれる。前半のクライマックスは「A WHITE DEEP MORNING」。杉林だろうか、森林の中を進むようなリアルな映像との融合を見せながら、演奏が熱を帯びる中盤以降で大量のスモークがステージから溢れ出すとともに紗幕が上がり、オーディエンスも立ち上がる。大げさに言えば天変地異、他の喩えをすれば現実世界にバンドが誕生したような感覚だ。罪や悔しさをひとりで押し殺している様子と、一歩踏み出す心境が伝わる、フィジカルなパフォーマンスと高度な演出が高い地平で融合した瞬間だった。
「空谷の跫音」、「Oneness」、「俤」などが、バンドという生き物の細胞や組成が変化してきたことがわかる現在の演奏で、時代を超えて刻み込まれる。前半のクライマックスは「A WHITE DEEP MORNING」。杉林だろうか、森林の中を進むようなリアルな映像との融合を見せながら、演奏が熱を帯びる中盤以降で大量のスモークがステージから溢れ出すとともに紗幕が上がり、オーディエンスも立ち上がる。大げさに言えば天変地異、他の喩えをすれば現実世界にバンドが誕生したような感覚だ。罪や悔しさをひとりで押し殺している様子と、一歩踏み出す心境が伝わる、フィジカルなパフォーマンスと高度な演出が高い地平で融合した瞬間だった。
淡々と刻まれるビートとリフの反復と影のあるメロディ。比較的最近の楽曲である「其限」も、この不器用なバンドが黙々と作り上げた一歩を思い出させたし、「汀に咲く」に溢れるジャンルでくくれないロックンロールの原初的体感も鮮烈だ。静の部分を抽出したセットリストではあるものの、さすがに「BASIS」では自ずとクラップが巻き起こり、声に出せないエナジーは多くの拳が物語っている。BRAHMANの民族音楽的な部分が、さらに日本の土着的な祭りの血と重なって聴こえてきた楽曲でもある。続く「鼎の問」では背景に福島第一原発が映る、美しさも恐ろしさも内包した福島の海の映像が見事にシンクロし、「ナミノウタゲ」では同曲のMVに登場する石巻市小渕浜の漁師たちの様子が映し出され、そこに今生きる人の強い表情とともにこの曲の持つ意味も更新されていく印象を受けた。抽象的な映像もドキュメンタリー的な映像も、あくまでも今、このバンドがどの楽曲を演奏するのか? にしっかり寄り添い、時に互いが軋轢を起こすほど強烈な化学反応を見せる。紗幕は上がっているのに、いい意味でメンバーの一挙手一投足を追わずとも、楽曲が伝えようとする核心が音と映像で迫ってくるのだ。もみくちゃのライヴハウスにはないホールのヒリヒリした感触。徹頭徹尾、必然しかない。
 中盤ではTOSHI-LOWやMAKOTO(Ba)が激しく動く楽曲も続き、ファンもその場でおのおの反応する。完全な着席スタイルだった前回ツアーに比べて、ホールとはいえ楽曲の激しさに応えることができる選曲でもあったのだ。そんななか、歌詞が投影されては崩れ落ち、バラバラになるという「ANSWER FOR...」の見せ方は、歌詞の内容と震えるほどのリンクを見せ、サビでは過去のモッシュ&ダイヴが行われていたライヴ映像が挟まれ、TOSHI-LOWも激しく動く。何が正しくて何が間違っているのか? 二元論ではなく、これまでも背負いながら進む意味合いがあったのかもしれない。
中盤ではTOSHI-LOWやMAKOTO(Ba)が激しく動く楽曲も続き、ファンもその場でおのおの反応する。完全な着席スタイルだった前回ツアーに比べて、ホールとはいえ楽曲の激しさに応えることができる選曲でもあったのだ。そんななか、歌詞が投影されては崩れ落ち、バラバラになるという「ANSWER FOR...」の見せ方は、歌詞の内容と震えるほどのリンクを見せ、サビでは過去のモッシュ&ダイヴが行われていたライヴ映像が挟まれ、TOSHI-LOWも激しく動く。何が正しくて何が間違っているのか? 二元論ではなく、これまでも背負いながら進む意味合いがあったのかもしれない。
「FAR FROM...」ではアロワナだろうか、巨大な魚がスクリーンに投影されることでさらに巨大で不気味に感じられ、スロー・テンポでロング・トーンの歌やギターの残響、乾いた諦念もある歌詞の世界と見事な符号を見せる。そのアウトロで再び紗幕が降り、メンバーの写真が投影されたときも再び鳥肌が立った。そして意外にも「Slow Dance」はラスト・ナンバーではなかった。この曲の前にマスク姿の街の群衆をはじめ、記憶に新しい去年の光景が映し出されたことが、この曲が生まれた背景を想起させる。民族的なギター・リフは狼煙のようでもあり、テンポ・アップしてループするビートはコンクリートという地面で踊り続ける私たちのダンス・ナンバーなのだ。"土壇場これも前哨戦で"というマインドセットに共鳴し、"静かに踊れ激しく Slow dance"という歌詞に鼓舞される。上がる心拍と同期するように実写やエフェクトのかかった映像、バンド・ロゴがカオスのように編集され、押し寄せる展開を見せたのだった。今回のツアーは『Slow Dance』のさらに先を見せていた。それが「旅路の果て」における、コロナ禍やそれ以前も含めて、この世を去った仲間との2ショット写真がいくつも投影される、もはや演出というより、楽曲とともにある表現だ。何ができるわけでもない、ただ誰かの存在があってここにいる。その誰かの命がけの戦いが今も自分を歩かせている――そんなふうに受け取ったらこみ上げるものがないなんて嘘だろうと思う。

長い拍手を受け、この日初めてTOSHI-LOWが言葉を発した。"誰もこんなことに慣れないなかで、俺たちはホール・ツアーを始めたが、やっぱり慣れないんだわ。昨日はワーってなりすぎて、あそこに穴が開いた(※前日の公演で、思い余って壁を強打)。よく言われた。「また2年前のあの頃のライヴができたらいいですね」。俺はそうは思わない。2年前に戻るのではなくて、あの頃の先に行きたい。その先に行って、新しい景色を見せねぇと、さっきスクリーンに出てきた仲間たちに申し訳ねぇ。良かったらまた遊びましょう。ようこそ俺たちのダンスホールへ"と、ラスト・ナンバーのタイトル・コールを兼ねた。その曲はなんとも初々しく、ティーンエイジャーが鳴らしそうな軽快といっていい初期衝動に溢れた1曲だったのだ。ひとりきりのダンスホールでも踊り続ける意思。でも、BRAHMANのライヴに行けばひとりきりじゃない。ヒリヒリした痛みや静かな憤りを内包して、今彼らは聴くものを踊らせる。比喩ではなく、踊らせる。ラストにスタッフが勢揃いした集合写真が映し出されたとき、この総力戦のライヴが視覚化された。数多くの頭脳と身体がバンドと息を合わせたからこそ、見ることができた"slow DANCE HALL"という表現。
2年前のその先に。言葉どおり、BRAHMANは完全にネクスト・フェーズにいたし、彼らだけのニュー・スタンダードを具現していた。今後、機会があればむしろファン以外のリスナーに体験してほしい。BRAHMANに抱くイメージはいい意味で粉砕されるだろう。
[Setlist]
1. 霹靂
2. 空谷の跫音
3. Oneness
4. 俤
5. A WHITE DEEP MORNING
6. 其限
7. 汀に咲く
8. LAST WAR
9. BASIS10. 鼎の問
11. ナミノウタゲ
12. ANSWER FOR...
13. 今夜
14. ARRIVAL TIME
15. FAR FROM...
16. Slow Dance
17. 旅路の果て
18. DANCE HALL
- 1