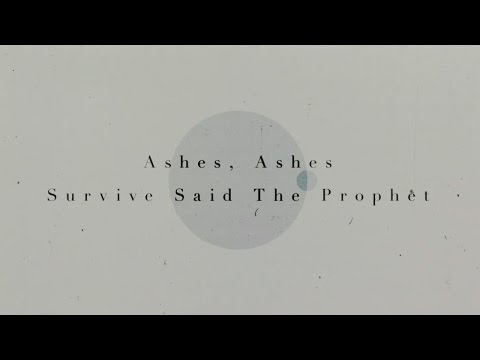INTERVIEW
Survive Said The Prophet
2022.02.01UPDATE
2022年02月号掲載
Member:Yosh(Vo) Ivan(Gt) Tatsuya(Gt) Show(Dr)
Interviewer:村岡 俊介(DJ ムラオカ)
Survive Said The Prophetが、待望のニュー・シングル『Papersky | Win / Lose』をリリース! 収録曲「Papersky」はTVアニメ"東京24区"オープニング・テーマ、もう一方の「Win / Lose」はプロ・バスケットボール"B.LEAGUE 2021-22 SEASON"公式テーマ・ソングというダブル・タイアップ両A面シングルということで、各タイアップに寄り添いながらも、同時に、現代をサヴァイヴするすべてのリスナーへ向けたポジティヴな想いが詰まった作品となった。今回、結成10周年を経て彼らが辿り着いた新たなマインドと、本作に込めたメッセージについて、4人全員に語ってもらった。
制限があることで逆に何かを生み出していく、クリエイティヴなマインドに変わっていっている
-去年のリテイク・ベスト・アルバム(『To Redefine / To Be Defined』)以来になるので、ちょうど1年ぶりですね。コロナ禍もいったん好転してはまた状況が変わるなど、不安定な情勢で音楽業界的にも大変な時期が続いています。そんななか、結成10周年を迎えた2021年を振り返ってみて、いかがですか?
Yosh:世間的に"サバプロそろそろ来るんじゃないか?"っていうワクワク感が、広がってきていて、"武道館"みたいなキーワードがリアルになってきたり、5枚目(2020年リリースのフル・アルバム『Inside Your Head』)で業界の人たちも"プロだよね"って認めてくれたりしているのを感じていたので、止まるとは思ってなかったですね。それがなくなったことに気づくのに時間かかったなって。心配はしていたけど、なんだかんだ言って"ここまで来られたから大丈夫でしょ"っていう感覚があって、半年くらい経たないとそのリアルな現状に気がつかなかったんですよ。それにやっと気づいたポイントがあって、そこで僕らがやらなければならないこととか、大事なものは何かっていうのを考える時間があって。それで向き合ったわけです。通常であればステージが用意されているから、ライヴをしていれば音で向き合う機会が絶対にあるんです。それがなくなって、自分たちにとって"うるさい音"がいかに大事だったかがわかったんですけど、"じゃあ、ライヴをしようぜ"というわけにいかないので、"音楽を作ってもっと発信できる体制になっていこうぜ"ってアクションに繋がって。諦めてしまうことは簡単なんですけど、このメンバーはそれを諦めさせてくれないメンバーなので、信じられるこの4人で乗り切れたっていうのが、2021年は達成感がありましたね。
-このコロナ禍において、バンドとしてまとまった、より強固な信頼関係ができたということですね。
Yosh:それはそうなんですけど、なんのために時間を取って向き合ったのかということが重要で。もちろん、スタートダッシュで駆け抜けるようなやり方もいいんですけど、そうじゃなく、コンティニュー・ボタンを押す前に立ち止まってみんなでディスカッションできたことが、これから次の10年の活動に繋がるんじゃないかと。
-次の10年に向けて再構築できた、というような感じですか。
Yosh:そうですね。
Show:Yoshの言う通り、コロナ禍でうまく立ち回れない状況になって、そもそも続けられるのか、ということから考えなくてはいけなくて。それが2020年より、2021年のほうがリアルでしたね。それからみんながそれぞれどういうふうに考えているのかを一度テーブルに出す機会があって。それまでは、お互いに牽制し合ってあまり会うことがない状況が続いていたんですよ。2020年は、コロナでライヴがなくなったことで、暇な時間ができてしまったので、いろいろ考えてしまって小さな亀裂ができていて、それを感じつつも何もできない状態で。それで2021年に入っていよいよ"どうしようか"ってことになって話し合って、"4人でこういうふうにしていこう"と話し合えたから、今バンドとしてより強くなれたんじゃないかと思います。それがなかったら、続かなかったかもしれないですね。そうやって向き合える機会があったから、今自信を持って"この4人でやってます"って言えるようになりました。
Tatsuya:2020年でぐちゃぐちゃになっちゃったものを、2021年で整理できて、どんどん繋げていったっていう感じですね。
Ivan:そうですね。世界の状況や、バンドの状況も含めて、ネガティヴに見がちだったんですけど、それをひとつのきっかけとして、もう一度自分たちでちゃんと考えることに繋がったので。
-なるほど。去年のツアー周りの話を聞かせてください。少し時を戻しますが、リテイク・ベスト・アルバム・タイミングでは、コロナの影響でツアー("Redefine Tour 2021")の前半戦ができなくなってしまうとか、時間変更などの制約もありましたが。実際回ってみていかがでしたか?
Ivan:まぁ、でもやっぱり"ライヴ最高!"っていうのは思いましたね。時間が流れていくのをリアルに感じたその気持ちを、音に出せたような気がします。当たり前なんだけど、"生まれたらいつか死ぬ"みたいなことも含め、自分もバンドも"今生きている"ということを改めて実感できたというか。
Yosh:もちろんこういう状況で、自分たちがやりたいイベントを計画しても、その通りにはならないし、"それでもいいからやらせてくれ"って言って実際やっても、うまくいくときもあれば"やっぱなんかな......"って思うこともあって。でも、乗り越えていかなきゃならないものが目の前にあって、そういった葛藤を音楽で表現するべきなのかどうかという恐れが、勇気に変わった瞬間はありましたね。制限されている状況で、"もっとこうだったら最高なのに!"って言うんじゃなくて、このハードルを使って、もっとできるんじゃないか、飛躍できるんじゃないかという考え方ができるようになって、理想の音が出せるまでは出し続けなきゃいけないんだって健康的な義務が生じたことで、前に進めるようになったんです。僕たちがシーンに出てきたときには、"もうお前らみたいなバンドはいくらでもいるよ"って言われてきて、それでも続けてきたバンドだからこそ、一番つらいこういう状況でも続けられる勇気が出たんじゃないかと。もう絶望にいることが簡単すぎて飽きちゃったというか(笑)。アルバイトをしていたインディーズのころのつらさに少し似ている状況でもあったので、"この抜け出し方はわかってるじゃん"って思えたんですよね。ひとりでただ悩んでいるのか、外に飛び出して仲間に会って奇跡を生み出すのかっていう。地球規模で逆らえない自然の圧力があって、それでも人類は生きているわけで。人類は進歩していっているんだから、無から何かを作り出すパンク・ロックの精神を今体現している感じですよね。
-前回の1年前のインタビュー(※2021年1月号掲載)でも、配信とか指定席とか、新しい形のライヴを開催することで、新しい何かが生まれることを信じてやっていきたいとおっしゃっていましたが、それは達成できたと思いますか。
Ivan:制限っていうと、もちろんネガティヴなものにはなるんですけど、制限があることで逆に何かを生み出していく、クリエイティヴなマインドに変わっていっているので。この時代の流れの中で自分たちをどう表現していくのかが、これからのアーティスト、ミュージシャンとしては必要なのかなと思いますね。
Show:自分の中では、"Redefine Tour 2021"はしこりのある感じで。しんどい時期のツアーだったんですが、それを解決する気持ちが消えてなかったのが救いだったかなと。そこで、さっきYoshが言ったみたいに諦めてしまうのは簡単で。諦めることを選ばずに、あえて苦しんだというのが、決断できるきっかけになったので、それがなかったら今はなかったなって気がしますね。
-そのあと、11月には全国6都市を回りましたね("something BOLD tour")。そのときは新体制でのツアーでした。
Show:答えを見つけるための期間だったなと思いますね。Redefineから11月のツアーまではみんなで対話する時間があって、詰めるものをいっぱい詰めて、そこに向かっていくという体制がしっかりできたのかなと。
-雨降って地固まるという。バンドを止めようかと悩んでいた時期もありましたが、そういう時期があったからこそ、今の結束があるということですね。
Show:そうですね。そこにみんなが行こうって思える気持ちになれた、その約9ヶ月間は意味のあるものだったなって。
-新体制での初ライヴはフェスですか?
Ivan:"SATANIC CARNIVAL 2021"ですね。
-そうですよね。その"SATANIC(SATANIC CARNIVAL 2021)"もそうですし、"百万石音楽祭2021~ミリオンロックフェスティバル~"や、"DEAD POP FESTiVAL 2021"も、様々な制限はありつつではありますが、なんとか無事開催できて。コロナ以前は当たり前のようにフェスに出演していたとは思うんです。しかし今こういう困難な状況が続いて、バンドもイベンターも、お客さんも様々な苦労を乗り越えて開催に行き着いていると思うんですよね。そういった意味では出演することに対してこれまでとは違った感慨深さがあったんじゃないかと。
Show:そうですね。僕ら出演者はもちろん、主催者もお客さんも、今までは毎年フェスがあるのが当たり前で。それができなくなってしまったときに、"どうしよう?"ってなって、みんながフェスを守っていくためにできることを真剣に考える、いいきっかけになったと思いますね。悪いこともあるけど、それだけじゃないというか。そのままでも続いていたとは思うけど、なぁなぁになって新しいことができなくなっていたりとか。そんなときに、引っ叩かれて目を覚まされたという感じですよね。
Yosh:その中でも、"DEAD POP(DEAD POP FESTiVAL)"っていうのは"いつか出たいな"って思っていたものだったので。
-意外ですが初めてですね。
Yosh:そうなんです。フェスっていろんな形がありますけど、先輩の中でも特にSiMは、いつもステージはキレッキレだし、そういうバンドがやっているフェスが、僕らの中ではグッとくるものがあって。イベントって規模が大きくなると、どこかでミス・マッチが起こってしまったりするんですが、バンドが主宰するとこんなにしっかりと意思が伝わるというか、固まるんだと思ったんです。さっきも出た"新しいフェスのかたち"っていうのもそうですけど、"不可能じゃねぇからな"って見せ方もカッコ良かったし、2日連続だったけど大変さも1ミリも感じさせなかったし、"やっぱかなわねぇな、俺たちまだまだだな"って感じて、エンジンかかったし。自分たちが"これから頑張らなきゃ"っていう重要なフェスでしたね。
Ivan:フェスを守っているというか、音楽を守っている感じで。全部抱えてあのステージに立つっていうか。
Yosh:SiMって厳しい状況の中でも音楽を続けてきたバンドじゃないですか。自分たちも、厳しい環境でやってきたバンドで、そういうことに誇りを持っているんです。今、世界的に音楽をやっていくのが大変な時代で、すごく試されていると思うんですよ。だから、彼らがカッコいいことを続けているかぎりは、自分たちもカッコ良くありたいなって。
Ivan:このコロナ禍でのクリエイティヴィティと団結感はすごかったですね。
-なるほど。劇的に変わっていくこの状況の中で、今、対バン・ライヴも激減してるじゃないですか。そうなると、他のバンドを観る機会が減ったり、他のバンドとの打ち上げもしなくなっている状況で。そんなバンド同士のコミュニケーションや、バンド・コミュニティも機能しにくいなか、こういったフェスへ出演することで、他のバンドのコロナ禍でのライヴの見せ方やモチベーションの保ち方など、バンド同士情報交換みたいなものはありましたか?
Show:このライヴがない状態がずっと続いていると、お客さんがライヴがないことに慣れちゃうんじゃないかっていう心配みたいなものがあって。でも、実際そんなことなくて、"これからも絶対音楽聴かせてくれ"っていうみんなの気持ちを知れました。
Yosh:オーディエンスのみんなが、ちゃんとルールを守って楽しんでくれてたのも驚きでしたね。音楽が欲しいから、きちんと自分たちで守っていくっていう気持ちが感じられてすごく良かった。そのリスペクトに答えていけたら、もっと大きなウェーヴになって広がっていくんじゃないかって思いました。
Ivan:それはこの100年とかで考えても、ほんと"今"しかない感動ですよね。
Tatsuya:貴重な体験だよね。
-それくらいポジティヴに変換していかないとダメですよね。
Tatsuya:それが新しいやり方として定着しつつありますしね。
Show:そうまでしてフェスに来たいのか、お前らっていう(笑)。そういう熱意を見ると、ほんと涙出ちゃいますよ。
-コロナ前に比べると、やっぱりハードル高いですもんね。
Yosh:ちょっと前まで"ライヴに行った"なんて周りに言うのも肩身が狭かったこのコロナ禍で、諦めずに情熱を持ち続けたそういう人たちがいるから、なくならないんですよね。そういう人たちにロックを忘れさせないためにも、自分たちは続けなきゃならない。Survive Said The Prophet(預言者は生き延びろと言った)ですね(笑)。









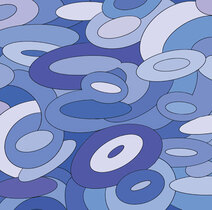



![s p a c e [ s ]](https://gekirock.com/diskreview/assets_c/2020/03/s_p_a_c_e_s_JKT-thumb-240xauto-53983-thumb-autox210-69432.jpg)