LIVE REPORT
Sumerian Records Presents "10 Years In The Black Tour"
2016.12.06 @Scottsdale, AZ Livewire
Writer MARINA ISAMI
約1ヶ月半かけて全米を巡ったアメリカの名門レーベル"Sumerian Records"の設立10周年を記念したツアー"10 Years In The Black Tour"。そのファイナル公演が、2016年12月6日にアリゾナ州スコッツデールのダウンタウンにあるLivewireで開催された。ツアー開始直前に、ヘッドライナーであるASKING ALEXANDRIAの衝撃的なヴォーカル脱退劇が起こり、何かと話題の多いツアーとなった今回。結果的には、AAの初代ヴォーカリスト Danny Worsnopの復帰もあってか、その発表後のチケットの売り上げは急上昇し、ソールド・アウトとなる公演も多数あったようだ。大規模なツアーの脇を固めるのはBORN OF OSIRIS、I SEE STARS、AFTER THE BURIAL、UPON A BURNING BODYと、どのバンドも実力派揃い。その中でも、このツアーで急成長を遂げたのが全公演でオープニング・アクトを務めたSumerian Recordsの新鋭、BAD OMENSである。2016年夏にセルフ・タイトルのデビュー・アルバムをリリースし、華のあるヴォーカリスト Noah Sebastianを中心に注目度も高く、公開したMVはどれも初日のうちに再生回数10万超えを叩き出していた。今回筆者は、ツアー初日となった10月25日のシアトル公演、そしてこのツアー・ファイナルの2公演に、彼らを追って参加することになった。
BAD OMENS
初日ではリハーサルが押し、観客の前でサウンド・チェックを行っていたBAD OMENS。なかなかレアだったそんな光景も、ツアー・ファイナルで見せることはなく、開演時間どおりにショーがスタートした。会場の照明が暗くなり、SEが流れ出すとフロアからは大歓声が。ツアー初日は約千人ほどが入るキャパシティだった会場が、ファイナル公演では2階席も合わせて約1万4千人ほどが入る会場となっており、初日とは明らかにファンの歓声の質が違うのがわかる。1ヶ月半近く回ったツアーでの彼らの急激な伸びやファン層の拡大は、遠く離れた日本から見ていても目覚ましいほどで、今か今かと待ち焦がれていたような声が会場内で爆発していた。
1曲目はゆったりとしたリズムから始まる「F E R A L」。ドラムのNick Folioはバンド内で最も小柄ながら、そのプレイはダイナミック且つパワフルなもので、見る者を一気に彼らの世界へと引き込んでいく。メンバーが次々とステージに現れ、最後にゆっくりとNoahが中央に現れると歓声は瞬く間に大きくなった。リズムに合わせ、ファンも一斉に大きく頭を振る。実は彼らは、この5ピースでのツアーは今回の"10 Years In The Black Tour"が初めて。そんな雰囲気を微塵も感じさせないほど息の合ったパフォーマンスを見せるバンドだが、やはりツアー中にその一体感は増したように感じられた。BAD OMENSのメンバーとして自身初のツアーとなったJoakim Karlsson(Gt)も、ステージを自由に動き回る。その勢いのまま、ウネるようなギターとリズムから「Exit Wounds」へ。曲調も一気にアグレッシヴなものに変わり、"跳べ! 跳べ!"と煽るNoahの声に合わせてフロアが大きく揺れる。曲中のブレイクダウン・パートでは、まだ2曲目にもかかわらず巨大なモッシュ・ピットが発生、会場内のボルテージもますます上がっていく。"ありがとう、本当に最高な夜だよアリゾナ。調子はどうだ? 「10 Years In The Black Tour」で今日ここに来ることができたのを嬉しく思っているよ。俺たちはBAD OMENSだ!!"と、胸に手を当てながら軽くお辞儀をするNoah。"次の曲は......"と言いながらスタートしたのは、美しいストリングスの音色が印象的な彼らの代表作「The Worst In Me」。サビでメンバーが手を上げれば、会場からはコールが起こる。これも初日では見られなかった光景だ。JoakimとVincent Riquier(Ba)がコーラスを担当し、もうひとりのギタリスト Nicholas Ryanがキレのあるシャウトを織り交ぜてくる。再びのMCで、Noahがこの日の全出演バンドの名前を叫び、彼らを称えるかのように手を上げコール。ライヴで必ずと言っていいほどNoahが見せるこのパフォーマンスには、彼の丁寧な人間性と、ひと目でオーディエンスを惹き込む魅力が表れている。また、Vincentの煽り方も実にうまく、彼のパフォーマンスもこのバンドのステージに欠かせないものだ。徐々に大きくなる前奏のあと、冒頭から叩きつけるようなリズムで始まる、アルバムの中でも屈指のキラー・チューン「Reprise (The Sound Of The End)」がスタート。疾走感のあるパートに合わせ、フロアの中央にできたサークル・ピットの勢いもますます加速していく。そしてラスト「Glass Houses」のイントロが流れると、会場からは大合唱が起こる。ファンのテンションもますますヒートアップし、煽りに合わせ一斉にジャンプしたあとは、ヘッドバンギングとモッシュの嵐が起こった。メンバー同士がとても仲が良いのも彼らの魅力のひとつであり、Noahがメンバーの肩を抱く場面も見られる。正真正銘、この巨大ツアーの最終公演で見せる最後の1曲――その気合のこもった音の数々を、ファンも全力で受け止め存分に暴れたツアー・ファイナル。晴れ晴れとした顔で何度も"ありがとう"と繰り返すメンバーの表情からは、このツアーをやり切った達成感を感じることができた。
終演後、"ツアーが終わるのが寂しい、それくらい素晴らしいツアーだったよ"と語ってくれたBAD OMENSのメンバー。レーベルメイトと過ごした日々、そして毎日のように新しいファンと出会えたこのツアーで得たものは大きかったようだ。2017年5月にはアメリカ・ウィスコンシン州で開催される巨大フェス"Northern Invasion"への出演や、ATTILAのヘッドライン・ツアーへの帯同も発表され、2017年もその勢いは増すばかり。"俺たちは止まらないよ。だからずっと見ていてほしいな"、そうしっかりとした口調で話したNoah。"日本にツアーで行ってみたい、今度は俺たちが会いに行くよ"とも笑顔で話してくれた彼らの姿を、日本の大きなステージで観れる日が来ることも、そう遠くはないように思えた。
UPON A BURNING BODY
故郷、テキサス州の空気を感じさせるようなアメリカンなSEとともに登場したUPON A BURNING BODY。このツアー開始直後に4thアルバム『Straight From The Barrio』をリリースした彼らは、そのスタイルも硬派なスーツ姿から一転、カジュアルな雰囲気にシフト・チェンジ。ツアー初日にRuben(Gt)に会い少し話を聞いてみたが、彼ら自身も最新作の出来にかなり満足しているようで、"気に入ってくれた!?"とニコニコと嬉しそうに話す姿が印象的だった。
ツアー後半からはセットリストの内容を変え、この日の1曲目は、3rdアルバム『The World Is My Enemy Now』から「Red Razor Wrists」を披露。咆哮にも近いファンの絶叫のなかでDanny(Vo)が登場し、サビでは会場中が一斉に手を上げて大合唱となった。そのままノンストップで始まったのは最新作より「B.M.F.」。リリース直後からMVの構成が話題になっていた今作の中でもかなり攻めている曲で、サビの"Hell Yeah!!"というフレーズに合わせてフロアからは噛みつかんばかりの力強い声が上がる。すでにダイバーも続出し、盛り上がりも凄まじいものに。続く人気曲「Scars」では、"サークル・ピット! サークル・ピットだ!"と叫ぶDannyの声に合わせて、フロアには巨大なピットが発生。身体の大きなアメリカンが一斉に走り出すその光景は危険度もMAX。曲に合わせてメンバーとファンが一斉にジャンプする光景も圧巻だ。メロディアスなサビでは手を上げシンガロングし、UPON A BURNING BODYらしい実にスタイリッシュで疾走感のあるステージを見せる。そして「Pledge Your Allegiance」へと続けば、フロアは大揺れとなり息をつく暇もない。2013年の来日公演以後に加入したTito Felixのドラミングもかなりの迫力で、彼のそのセンスに思わずシビれてしまう。"最新作、聴いてくれた奴はどれくらいいるんだ? 手を上げてくれ!"とのDannyのMCから、ラテン調のノリの良いリズムが流れ、そのまま全員で手拍子。最新作から「Already Broken」、そして彼らの代表曲とも言える「Texas Blood Money」の爆発せんばかりの勢いそのままに、「Sin City」でラストとなった。
AFTER THE BURIAL
2015年はギタリストの脱退と死別もあり、ライヴ出演をキャンセルするなど災難に見舞われたAFTER THE BURIAL。しかし2016年2月にアルバム『Dig Deep』をリリースし、その勢いは再び凄まじいものになっている。このツアーでも初日からフロアを破壊せんばかりのモッシュ・ピットを起こし、化け物のごときステージを展開していた彼ら。この日もフロアに入って撮影することが困難になるほど、ステージ前に人が押し寄せている状況だった。目の前に光が差してくるような明るい前奏から始まる「Aspiration」でメンバーがステージ・イン。"みんな、調子はどうだー!? 跳べ!!"と叫ぶAnthony Notarmaso(Vo)の声に合わせて観客も大きく波打つ。このバンド特有とも言える、Trent Hafdahlの激しく切り刻む8弦ギターのカッティング音が耳にガリガリと響いてきた。今は4人編成となってしまったが、以前と変わらないライヴのクオリティの高さに、思わず言葉を失ってしまう。「Your Troubles Will Cease And Fortune Will Smile Upon You」では、めまぐるしい音の変化と激しい照明の明暗が続き、まるで異次元にでもいるかのような気分になってくる。しかしMCになった途端、さっきまで鬼のようなステージを見せたメンバーが案外穏やかに喋る姿も印象的。Trentがちょこちょことユーモアのあるギター・フレーズを挟んでくるのもまた面白い。そんなメンバーに対してファンからは"ATB! ATB!"と次々に声が上がる。"次の曲は新しいアルバム『Dig Deep』からだ! 声出せる奴はわかってるよな? 叫べ! 暴れろ!"と、東南アジアを思わせるような独特なギター・フレーズから始まる「Lost In The Static」へ。"次の曲も『Dig Deep』からだ。ここにいる奴ら、どれぐらいこのアルバムを聴いてくれたかい? 手を上げてくれ......OK、最高だ。お前ら、左右に分かれろ! 約束する、全員これでもかってくらいの笑顔にしてやるよ!"と煽ると、「Collapse」で巨大なウォール・オブ・デスが出現。彼らのライヴには、会場を破壊するんじゃないかと思うほどのパワーがあり、このファイナル公演でのフロアの盛り上がりも凄まじいものだった。"次の曲はクラウドサーフにもってこいの曲じゃないか? 最後まで全力でぶつかってこい!"――そう叫び始まったのは、2013年リリースのアルバム『Wolves Within』から「Anti-Pattern」だった。引きずり込まれそうな前奏、変拍子ながらもまったく狂いのないDan Carleの激しいドラミング......そこから一気に叩き落してくるようなプレイを聴かせる。そして、新作を無事にリリースできたこと、このツアー終盤でサポート・ベースのAdrian Oropezaが正式加入となったこと、2017年にはEMMUREとのヘッドライナー・ツアーを行うこと――そのすべてへの感謝をAnthonyが語る。ラストの「A Wolf Amongst Ravens」まで、フロアを蹂躙し尽くした彼らの音に盛大な拍手がいつまでも贈られていた。
I SEE STARS
最先端を行くような曲を次々と発表し、2009年のアルバム・デビュー当時から何かと注目度の高いI SEE STARS。2015年にはメンバー2名の脱退が発表され、現在は4人体制で活動をしている彼ら。まるで心電図のような機械音とキーボードの美しいメロディから始まる「Break」でショーがスタート。バンドの顔でもあるクリーン・ヴォーカル Devin Oliverの人気はかなりのもので、彼がステージ中央に現れると黄色い歓声が湧き起こった。長身で軽やかにステージを動き回るDevinの一挙一動にファンは応え、フロアとの距離を感じさせないほどの一体感がある。そのままリズムに合わせ大きく手を上下に動かすと、「Ten Thousand Feet」で先ほどとは曲調が一転、ブレイクダウン・パートではフロア中央にモッシュ・ピットも発生した。キレのあるエレクトロ・サウンドとギターのリズムから始まる「Running With Scissors」では、Andrew Oliver(Vo/Key/Prog/Per)とDevinが交互に歌ったりハモったりしつつ、サビでは壮大なシンガロングが会場内に響き渡った。4人編成になったぶんシンプルなステージになった印象はあるが、スクリームも担当するようになったDevinの声の使い分けも上手く、まったく見劣りしない。囁くような歌い出しから壮大なメロディへと続く「Calm Snow」で、Jeff Valentine(Ba)とDevinの合図に合わせてフロアの全員が手を上げ左右に大きく振る光景も、この曲の雰囲気にマッチしていてとても美しい。そこから「All In」、「Murder Mitten」、「Mobbin' Out」と近年のナンバーを披露。デビュー当時は全員がまだ10代だった彼らも、作品をリリースするごとに様々な表情や音楽性を見せ、大人の雰囲気を見せるショーをするようになり、今回のツアーではエレクトロコアやダンス・ミュージックからバラード的要素を取り入れたものまで、全体的に緩急のメリハリをつけた選曲になっている印象であった。
BORN OF OSIRIS
SEが流れ始めた時点で会場内の空気が変わったのがわかる。今やSumerian Recordsの代表格ともなったベテラン、BORN OF OSIRISはオープニング・ナンバー「Bow Down」でのいきなりのブレイクダウンからその世界観を展開。フロントマン Ronnie CanizaroとJoe Buras(Key)が中央に現れ獰猛なスクリームをかますと、スイッチが入ったかのようにフロアは大暴れである。変則的なリズムのイントロで始まる「Empires Erased」では、バンドとしての総合力はもちろん、個々の技術力やパフォーマンス力の高さを見せつけられる。キーボードとヴォーカルを担当し、ステージを縦横無尽に動き回るJoeの曲世界への入り込みようは、もはやクレイジーだと言ってもいいほどの迫力がある。Ronnieのどっしりとした野獣のようなグロウルも安定感は抜群で、Cameron Losch(Dr)とDavid DaRocha(Ba)も変調が交ざりながらも小刻みに正確な音を叩き込んでくる。シンセサイザーの神秘的なメロディを織り交ぜながら始まる「Goddess Of The Dawn」では、バンドの中心人物でもあるLee Mckinney(Gt)の狂いのないタッピング・プレイから繰り出されるソロ・パートも素晴らしい。凶暴なギター・リフから始まる「Open Arms To Damnation」、そしてシンセサイザーの突き抜ける音が眩しい「Throw Me In The Jungle」ではサビに合わせてフロアは大合唱。メンバーが全員がお立ち台に上がり両手を広げ観客を煽る姿はもはや神々しくさえ見える。"まだいけるだろお前ら!"と初っ端からモッシュ・ピットをフル回転させる「Abstract Art」のエンディングからそのまま機械音と少しクラシカルな前奏が流れ始め、人気曲「Machine」へ。"最高だよお前ら! もっとヤバいくらいに狂えるって奴、声出してくれ"と煽りから会場のボルテージもMAX状態で、クラウドサーフが乱立する。ラストの「Follow The Signs」までの怒濤の展開にフロアが熱狂し、その風格を見せつけたショーとなった。
ASKING ALEXANDRIA
初日公演でも感じたことだが、やはりトリのASKING ALEXANDRIAの人気やステージングは、すべて格が違った――そのひと言に尽きる。2015年にバンドを離れたDanny Worsnop(Vo)はソロ活動をスタートさせ、Denis Shaforostovを新ヴォーカリストとして迎えたバンドはアルバム『The Black』を制作。彼らは完全に別々の道を歩んでしまったのだと思われていた。しかし2年という月日の後、DannyはASKING ALEXANDRIAのメンバーとして再び同じステージに立つ。世界中から注目されたその最初の公演が、今回の"10 Years In The Black Tour"である。SEも流れないうちから会場中のDannyコールが止まらない。絶叫にも近いその歓声の中、ついに彼らのツアー・ファイナルが幕を開けた。
オープニングSEとして「Welcome」が流れ、ライトの瞬きと共にメンバーがひとりずつステージに現れる。勢いよく噴射したスモークの中で激しいスクリームを披露しながらDannyが登場。大歓声の中、そのまま「Dear Insanity」が始まると、早くもフロアは暴動のような状態になり、サビになるとまずDannyは上手にいるギタリスト Ben Bruceのもとへ。肩を寄せ合い笑顔で歌うふたりの姿は、何も変わらない昔からの親友そのもの。表情がクルクルと変わるBenの晴れやかな表情は、初日に見たそれよりもさらに輝いていた。そこから「To The Stage」、「Someone, Somewhere」と、ファン馴染みの曲が次々と演奏される。それぞれのメンバーに寄り添い、時にはフザけてちょっかいをかけるDannyだが、その歌の上手さは間違いなく本物。初日公演で聴いた、ASKING ALEXANDRIAとしての2年ぶりの彼のクリーン・ヴォイスには、鳥肌が立つほど感動してしまった。"毎回これを言ってるんだけどさ、そう、俺は戻ってきたぜ!"とDannyが言葉を発するたびに、ファンは手を上げ、張り裂けんばかりの叫び声を上げる。"今夜はみんなを素敵な旅へと案内しよう。そう、俺たちASKING ALEXANDRIAの、これまでのアルバムの曲をお届けする素敵なショーの時間へね"――時には別人のような声も出す、緩急のついたDannyの語りはまるでコメディアンかと思うほどに面白く、とても惹きつけられる。このMCもきっとファンの楽しみのひとつなのだろう。Benが現れ、"ねぇDanny、その話面白くないんだけど......"とお互いにイジり合う姿も微笑ましい。その姿を後ろでにこやかに見つめていたJames Cassells(Dr)の合図から「Run Free」がスタートし、サビでは会場中からシンガロングが巻き起こる。壮大な曲の終わりから、そのまま爆発するかのようにキラー・チューン「The Death Of Me」が始まると、巨大なサークル・ピットが発生。熱狂するファンの勢いもまた、まったく衰えることがない。最後はアカペラでしっかりと締め、一度暗転。再び照明がつくと、楽器を持たない状態でメンバーがステージに集合し、"10 Years In The Black Tour"を開催したレーベルへの感謝と祝いの言葉を述べる。それと同時に、手にしていたシャンパンや大ビンの酒を客席へ向けて撒き散らすところは何とも彼ららしい。そしてDannyがアコギを手に取り、全編クリーン・ヴォイスのロック・チューン「Moving On」を披露。1万人もの観客が共に歌い、一斉に手を上げる光景は圧巻である。カメラを向けると必ずと言っていいほど笑顔を向けてくれる、縁の下の力持ち的存在のベーシスト Sam Bettley。落ち着いた表情で正確なプレイを披露する、もうひとりのギタリスト Cameron Liddell。見ていて思わず笑顔になってしまうほど、メンバー同士の仲の良さが溢れ出ているショーである。
しっとりした雰囲気からテンポの良いリズムに切り替わると「The Road」へ。ブレイクダウン・パートではクラウドサーフが大量に発生、フロアも大きく左右にウネる。かと思えばMCでは、急にカバー・ソングを披露したり、ドラム・ソロの無茶振りをしたりと、もはやフリーダム状態。"ラスト2曲だ!......で、何やる?"、"うーん......「A Prophecy」?"――そんな掛け合いからスタートしたのは、彼らの代表曲のひとつである「A Prophecy」。2階のバルコニーから身を乗り出して観ていたファンの中には涙を見せる人もチラホラ。そして"ラスト1曲だ!"のコールから「Not The American Average」へ。BenとCameronが背中を合わせたり肩を寄せ合ったりして、息もぴったりに演奏する姿を見せる。終盤の叩き落すようなブレイクダウンでは、Cameronの合図に合わせてウォール・オブ・デスが発生。ステージ上ではBenがシンバル・スタンドをすべてなぎ倒し、それを見たDannyはステージのお立ち台をすべて引っくり返し始める。大歓声とドラム・ロールの中、大きく会場のファンへ一礼をし、メンバーはステージをあとにした。
アンコールの声が掛かると、しばらくしてひとりステージへ戻ってきたDanny。ファンのコールに合わせて着ていたTシャツを破り捨て、ファンがステージに投げ入れたTシャツに着替えてみたりと、本当にノリのいい奴である。彼はここで改めて今回のツアーと会場のファンへ向けて感謝の言葉を述べる。そして、I SEE STARSのDevinをステージに呼びつけて乾杯をしだすなど、最後までとにかくステージを楽しんでいる姿を見せる。
"この2年間は、俺は決して無駄じゃなかったと思ってる。そしてこうやってまた俺たちは集まることができた。離れていた2年の間、俺はひとりでいろんなことを考えることができたし、人間的に成長できたと思ってる。また次のステージへこの全員で進むことができるんだ。ラスト2曲、本当にこれで最後だ。1曲目は俺たちの1stシングルで、最初のミュージック・ビデオになった曲だ。みんな、俺のあとに続いて一緒に歌ってくれるか?"――そんな言葉を挟んだDannyが、メンバーひとりひとりの名前をコール。その声に誘われてメンバーが再びステージに揃うと、もちろん次にプレイされたのは「The Final Episode (Let's Change Channel)」だ。どこにそんな力が残っていたんだ!? と目を疑いたくなるほど、会場の盛り上がりは最高潮に。"Oh My God!"のコール&レスポンスでは、会場が揺れるほどの大合唱が起こり、ファンが一斉に手を振り上げる。"ありがとう! 本当にありがとう!"――そのままラストの「A Single Moment Of Sincerity」へ。ファンに笑い掛け、メンバー同士も時折笑顔を交わしながらショーは終わりへと向かっていく。ラストのブレイクダウンでは再び巨大なウォール・オブ・デスが発生。拍手と歓声に包まれる中、メンバーがファンと視線を交わし何度もありがとうと告げながら、"10 Years In The Black Tour"最終公演は幕を閉じた。
"これが俺たちASKING ALEXANDRIAだ!"――そう、"まさにあるべき姿に戻った"という表現がしっくりくるほど、彼らの中に2年間の溝は感じられなかった。今回のツアー・ファイナルでは統一感や仲の良さが見えるパフォーマンスもさらに増え、その絆を取り戻していたように感じる。彼らのことをそんなに詳しく知らない私でさえ、この姿がいつまでも壊れないでほしいな......と心から願うほどに素晴らしいショーを、Sumerian Recordsの看板を背負い披露してくれたツアーだった。
- 1



























































































































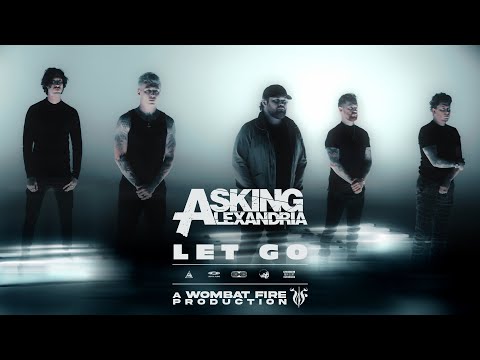


































![The Death Of Peace Of Mind + Concrete Jungle [The OST] (Japanese Exclusive)](https://m.media-amazon.com/images/I/51aMg1TCS8L._SL500_.jpg)














































