INTERVIEW
Unholy Orpheus
2024.05.28UPDATE
2024年05月号掲載
Member:紫煉(Scream/Gt) 仁耶(Gt) Jill(Vn) Hiroyuki Ogawa(Ba) FUMIYA(Dr)
Interviewer:杉江 由紀
デス・メタルとはなんぞや? という問題提起に対して一石を投じるような作品。それを"あんきも"ことUnlucky Morpheusの別業態にして新業態となるUnholy Orpheusが、今ここに1stアルバム『what is DEATH?』として完成させるに至った。あんきものメイン・ヴォーカリストであるFukiは1曲にゲスト参加しているものの、全編を彩るのは紫煉の発するデスボであり、仁耶のテクニカルなギター・ワークに、Jillの華麗なるヴァイオリンの音色、さらにはHiroyuki Ogawaのグルーヴィなベースと、FUMIYAの精緻にして頼もしいドラミングにほかならない。メロディック・デス・メタル・プロジェクトを標榜するUnholy Orpheusがここに見参!
-このたび、1stアルバム『what is DEATH?』を発表することになったUnholy Orpheusは、Unlucky Morpheusのメンバーによるメロディック・デス・メタル・プロジェクトになるそうですね。今年はあんきもにとって15周年の節目でもありますが、ここに来て新たな展開をしていくことになった経緯をまずは教えてください。
紫煉:15周年だから新しいことをやってみようみたいなところはあんまり関係がなくてですね。今回このプロジェクトでアルバムを出すことになったのには複合的な理由があって、まず2020年7月にUnlucky Morpheusとして出したアルバム『Unfinished』っていうのが、デス・ヴォイスを結構入れ込んだ感じの作風だったんですよ。
-たしかに、現在のライヴでもキラーチューンになっている「Top of the "M"」をはじめとして、デス・ヴォイスを生かした楽曲が多く収録されていた印象はあります。
紫煉:あの『Unfinished』を出して、ライヴとかもやって、次に何をやろうかな? って考えたとき、前作の『evolution』(2022年リリースのフル・アルバム)では『Unfinished』でやったことを両極端なかたちで二分化させて、まずはフッキー(Fuki)のクリーン・ヴォーカルが主軸になる作品を作ってみたんですよ。そして、今回の場合はもうひとつの側面である、Unlucky Morpheusのよりヘヴィな部分を集約させたアルバムを作っていこう、と考え出したところがスタートでした。理想を言えば、『evolution』と同時発売とかあんまり間を置かずに出せれば良かったんですけど、今回のアルバムは制作に時間がかかっちゃったこともあり、このタイミングでの発売ということになりました。
-そうした作品を、Unlucky Morpheusとしてではなく新プロジェクト、Unholy Orpheusとして発表するということについて、メンバー内では何か意見が交わされるようなことはあったのでしょうか?
Ogawa:いや、普通に"あぁ、そうなんだー"って(笑)。以前には、楽器隊の4人でQUADRATUM From Unlucky Morpheusとして別プロジェクトを立ち上げて、『Loud Playing Workshop』(2021年)っていうカバー・アルバムを出したこともありますしね。僕としては、そういう流れのひとつなのかな? って感覚でした。
-Unholy Orpheusはメロディック・デス・メタル・プロジェクトであるだけに、Fukiさんは在籍していらっしゃいません。今作『what is DEATH?』では、「TRAUMATA (feat. Fuki)」にて"ゲスト・ヴォーカリスト"として参加してくださっていらっしゃるのですね。
紫煉:そこはちょっとツッコミ待ち的に"ゲスト・ヴォーカリスト"、"feat. Fuki"っていうかたちにしてるところもあります(笑)。
-それにしても、このUnholy Orpheusというプロジェクト名がまた実に絶妙ですよね。文字の並びとしては似ているようで意味はまったく違うあたりが素晴らしいです。
紫煉:もともと、今回の『what is DEATH?』に11曲目として入れた「want to LIVE」は、2022年5月にMVを単体で公開してたんですね。そのときの名義は"Shiren from Unlucky Morpheus"というのを使っていて、今回も別にそれでいいかなとは思っていたんですが、アルバムを出して配信もするとなったときに、実務的な面で、アーティスト名に"from Unlucky Morpheus"ってついちゃうと、手続きがいろいろ複雑になってしまうことがわかったんですよ。それで、今回は思い切って新しいプロジェクト名を付けることにしたんです。それも、見るからにあんきもと関わり合いがあるってわかる名前にしました。たぶんCD 屋さんでたまたま見かけた人がUnlucky Morpheusのことしか知らなかったとしても、Unholy Orpheusって書いてあったら"これ、あんきもの人がやってんのかな?"となると思うんですよ。
-間違いなく、これは空目してしまうと思います(笑)。おそらく、ショップでもあんきもの隣に並べられることになるでしょうしね。
紫煉:そうなんですよ。さっきも話に出てたQUADRATUM From Unlucky Morpheusも含めて、いろいろ名義が増えすぎちゃうとわかりにくくなっちゃうのもありますし、そのへんの問題とかをなるべく解消しようと考えた結果、Unholy Orpheusという名前にしました。
-そんなUnholy Orpheusの1stアルバム『what is DEATH?』は、全11曲のフル・ボリュームな内容となっておりますが、明確に"メロディック・デス・メタル"という方向性が示されているだけあって、今回はやはり各メンバーとしても、そのことを意識したうえでレコーディングされていくことになられたのでしょうか。
FUMIYA:メロディック・デス・メタルを軸にしてやるとなったからには、やはりUnlucky Morpheus本体からはドラムが一番わかりやすく変わったと思います。テンポ的に言えばBPMは速くなりますし、フレーズとして入れ込む要素も普段とは違いました。紫煉さんに匹敵するくらい僕もメロディック・デス・メタルは大好きで、これまでには実際そういうバンドもTHOUSAND EYESしかりやってきているので、そこで培ってきたエッセンスというのを飛び道具も含めていろいろ出せましたし、個人的なこだわりもたくさん入れながら作っていくことになりましたね。ただ、この作品に関して言うと僕はいわゆるメロディック・デス・メタルだとは思ってません。曲調によってはマンソン(MARILYN MANSON)的なインダストリアルっぽい曲調のものも入ってますし、Djent的なキック・フレーズが入っている曲もあるので、デス・メタルという多岐にわたるジャンルを1枚で体現したアルバムになったんじゃないかな? って気はしてます。ドラマーとしても、バラエティに富んだプレイをすることができました。
紫煉:"メロディック・デス・メタル"というジャンルに特化したアルバムというよりは、"メロディックなデス・メタル"をいろいろやったアルバムかも(笑)。
仁耶:あんきもがやるデス・メタルっていう感じだよね。
Ogawa:でも、個人的にはあんまりあんきもの延長線上っていう感覚はないかもしれないです。あんきものほうも短距離走な感じはあるんですけど、Unholy Orpheusはより激しいダッシュを求められるというか。これを仮に50歳とか60歳になってもやるとしたら、かなり大変だろうなっていう感じがしますね。たぶん今がギリギリなんじゃないかなと(苦笑)。
FUMIYA:今やるしかないなっていう感覚は僕もわかります。
Ogawa:非常にオフェンシヴな守りに入ってないスタイルですからね。あんきもは激しいものもありつつ、バラードもあり、ミッド・テンポもあってというわりと多彩な音楽性を持っているバンドですが、Unholy Orpheusはまさに攻撃特化型なんですよ。そのことは、年末に1回あんきものオープニング・アクト、Shiren from Unlucky Morpheusとしてライヴ("15th Anniversary Live 『UnluckyMorpheus Festive Overture』")をやったときにより実感したところがありました。
-ギタリストの仁耶さんからすると、Unholy Orpheusとして音を出していく際に、メロディックな部分を特に意識されたところはございましたか。
仁耶:僕としてはまったく新しいことをやるというよりは、いつもの延長線と捉えていたところがありますね。そもそもあんきも自体、メロディック・メタル・バンドにしてはDjentとかデス・メタル的なエッセンスを多めに取り入れているバンドなんですよね。なので、Unholy Orpheusに関してはヘヴィなギター・リフの割合がいつもよりは多めかな、という感覚でやってますね。大筋ではあんきもとあまり変わってはいないけど、ステータスの振り分け方が違う感じです。
Ogawa:え? 今の語尾の"です"は"DEATH"っていうふうに書いてもらったほうがいいやつ?
仁耶:日本語で大丈夫です(笑)。
-さて。Unholy Orpheusの楽曲においてメロディックな部分を醸し出すパートとしては、ヴァイオリンの担っているところも相当に大きいと思うのですが、Jillさんは今作『what is DEATH?』を仕上げていく際、そのあたりをどのようにお考えでしたか。
Jill:普段のあんきもでもヴァイオリンでメロディックな部分を出していくことは多いですが、Unholy Orpheusの曲にはわかりやすい歌のメロディというものがないぶん、ヴァイオリンでメインのメロディを奏でていくことがとても多いです。繊細なニュアンスをどう出していけばいいかということは自分でも研究しましたし、紫煉さんとも相談しながら、歌メロを作っていくようなつもりで音を作っていきました。
紫煉:ほんとに今回はヴァイオリンが主旋律を奏でてることが多いですね。
-外部から奏者を呼んで弾いてもらうのとは違って、今作『what is DEATH?』は、メンバーにヴァイオリニストがいる利点を存分に生かした音源になっている印象です。
紫煉:そこは曲作りの段階から、Unholy Orpheusならではのやり方をしていったところがあったんですよ。あんきもの場合は、歌メロがあってヴァイオリンの対旋律があって、さらにギターがそこに時折絡みついていくので、同時に3本のメロディが出てくるケースも結構あるんです。そうすると縦のラインが複雑になるんで、横のラインはシンプルにして作っていくことを心掛けているんですけど、Unholy Orpheusの場合は、僕の歌ってるヴォーカル・パートにはメロディ・ラインがないので、主旋律は基本的にギターとヴァイオリンの2ラインになるんですね。そのぶん、こっちではリズムや曲展開といった横のラインを複雑にすることがバランス的に可能になるというか、Fukiの枠が空くぶん今までとは違うアプローチをやってみています。そういう意味でも、このアルバムは俺だけが目立つShiren from Unlucky Morpheusではなくて、5人それぞれに見せ場がある作品になっているからこそ、Unholy Orpheusとして出すことができて良かったと思います。
-なお、曲作りの段階で、紫煉さんがメロディの部分以外で重視されていたことは他に何かありましたでしょうか。
紫煉:時短ってことですかね。今ってどのエンターテイメントも時短が求められてるところがあると思いますし、実際このアルバムは35分くらいなんですよ。
-内容が濃いせいか、とてもそうは聴こえません。
紫煉:体感だと50分くらいに感じるでしょうね。そこはやっぱり、ちゃんとフル・アルバムを聴いたという満足感を得られるような情報量を入れていくようにしたんですよ。これは普段の曲作りで常に意識しています。







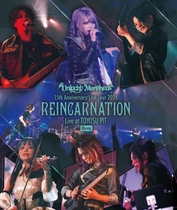









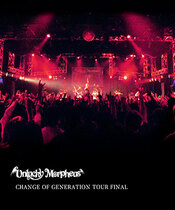
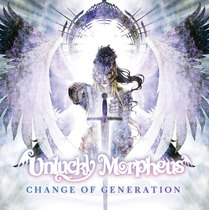
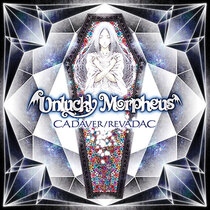
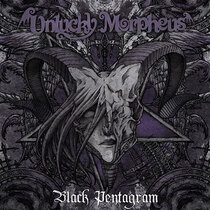



![[Official MV] Unlucky Morpheus「万華鏡」](https://i.ytimg.com/vi/bMSpe_3ONV4/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「Convergent Rays」](https://i.ytimg.com/vi/S4sjdgG8aIs/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「SAKURA chevalier」](https://i.ytimg.com/vi/0yd4GsVT3GI/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「世界輪廻 (Sekai-Rinne) 」](https://i.ytimg.com/vi/FmCRJKZGDvM/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unholy Orpheus「Undeveloped Land」](https://i.ytimg.com/vi/78-9oDvG0Ms/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「U.F.O. - U Feel Overjoyed! - (Unlucky Morpheus Cover Ver.)」](https://i.ytimg.com/vi/64jyNQzidaU/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「アマリリス」](https://i.ytimg.com/vi/RQpz80bu-rA/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「Welcome to Valhalla」](https://i.ytimg.com/vi/gwJZefZr0nI/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「The Black Death Mansion Murders」](https://i.ytimg.com/vi/UyxM03zOC1M/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「"M" Anthem」](https://i.ytimg.com/vi/WoUzaVI0paY/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「"M" Revolution」](https://i.ytimg.com/vi/Xza4IGEqTIs/hqdefault.jpg)




![[Official MV] Unlucky Morpheus「Top of the "M"」](https://i.ytimg.com/vi/g7idmlQY0mw/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「Carry on singing to the sky」](https://i.ytimg.com/vi/UlpAWv1PQ8w/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「Unending Sorceress」](https://i.ytimg.com/vi/PCv3s0T4bx0/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「瀧夜叉姫」](https://i.ytimg.com/vi/YXsCQ0rGK_g/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「籠の鳥」[シーエ・3DMV]](https://i.ytimg.com/vi/k1JmrU3DT54/hqdefault.jpg)
![【2D】[Official MV] Unlucky Morpheus「KIZASI」](https://i.ytimg.com/vi/pu2QqwEvpSk/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「Knight of Sword」](https://i.ytimg.com/vi/TiQdl2toBtg/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「CADAVER」「REVADAC」](https://i.ytimg.com/vi/gxN3L2jrrEI/hqdefault.jpg)
![[Official MV] Unlucky Morpheus「Black Pentagram」](https://i.ytimg.com/vi/V8i_QhOgsKw/hqdefault.jpg)



























![[ROCKAHOLIC Presents"ROCKAHOLIC 15年祭 -BEYOND THE ROCK-"]](https://gekirock.com/livereport/assets_c/2025/12/15th_beyond_the_rock-thumb-160xauto-128564.jpg)


![[GEKIROCK CLOTHING Presents"WEAR THE MUSIC"DAY1]](https://gekirock.com/livereport/assets_c/2024/07/wear_the_music_day1-thumb-160xauto-112861.jpg)







