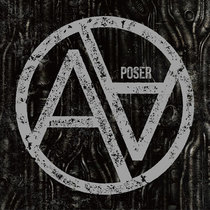INTERVIEW
上田剛士(AA=)
2023.03.23UPDATE
2023年03月号掲載
Member:上田 剛士(Ba/Vo/Prog)
Interviewer:吉羽 さおり
ひとつひとつのバンドの存在意味があって、代わりがない。そこがパンク・ロックの重要な部分で、自分も影響を受けているところでもある
-今SID VICIOUSの名前が出ましたが、当時の自分のベース・ヒーロー的な人はいたんですか。
特にこの人というのはいないんだけど、やっぱりTHE STALINとかが好きだったので、(杉山)シンタロウさんとか。アレルギーだったら、女性のU子さんがベースで。パンク・バンドのベースって、なんというか立ち位置がかっこいいんですよね。そんなに一生懸命やらなくてもかっこいい感じになるというか──まぁ、これはSID VICIOUSがいけないんだろうけど(笑)。
-ベースを見え方にしてしまったと(笑)。バンドに加入してからは、曲作りの面白さにも目が向いていくんですか。
そうですね。すぐにオリジナル曲を自分で作るようになっちゃいました。
-というと、ここに並ぶようなパンク・バンドのような曲ですか。
最初はいろいろですね。言っても高校生の頃には全部作れないんだけど、そのあとはスタジオでアルバイトをしていたので、身近に録音機材とかがあったんです。MTR、リズムマシンで打ち込みで曲作りを始めて。当時は、いわゆる今では名機と言われるようなリズムマシンが出たり、簡単に使えるものとかが出てきた時代だったんです。自分としてはそこからそのまま、今のコンピューターベースのものに地続きで繋がっているので。その時代のMTRとドラム・マシン、MIDI機器が手軽に使えるようになったのは大きかったんじゃないかなと思います。
-今回、DEAD KENNEDYSの「California Uber Alles」がカバーされましたが、のちにヴォーカルのJELLO BIAFRAは、LARDをスタートしてインダストリアルなサウンドにも繋がっていくことも面白いですよね。そこも上田さんの音楽には通じていきますし、1本筋が通った感じがあるというか。
そうですね。のちにMINISTRYとかが好きになったんだけど、それは完全にその流れからしたね。DEAD KENNEDYSが好きで、JELLO BIAFRAが好きで、LARDを聴いて、なんじゃこりゃ! っていう。で、どうやら一緒にやっているのがMINISTRYってバンドらしいぞと。
-今回の海外バンドのカバーでは、DEAD KENNEDYS、SEX PISTOLS、そしてTHE CUREというこのばらけ方も面白い。
THE CUREは立ち位置的にはメジャー感があったり、"ベストヒット USA"的なところにもいるんだけど、自分的には同じ括りの世界にいた感じですね。パンクからポストパンクの世界に入っていったもののひとつかなと思いますね。
-THE CUREが宿している切なくメランコリックで、でもポップ性の高い音楽というのは特有なものでしたね。
これがたまらないんですよね(笑)。それで、ちょっとやってみようかなというのでやったら、楽しかったので収録しました。
-アルバムで言うと、シーナ&ザ・ロケッツの「ユー・メイ・ドリーム」からTHE CUREの「In Between Days」へという流れは、まるで決まっていたかのような美しい並びで。さらに、続くイヌの「メリーゴーラウンド」からは、ディープでエクスペリメンタルなゾーンにも入っていきます。特にアンサンブルの妙も聴きどころですが、今作でレコーディングにはどんなメンバーが参加されているんですか。
以前コラボ曲(2019年リリースの7thデジタル・シングル「DEEP INSIDE」)も出しているHIROSUKE(BALZAC/Vo)さんや、AA=のメンバーも参加しているんですけど、イヌの「メリーゴーラウンド」にギターで参加してくれているのが、BUCK-TICKの今井 寿さんですね。ちょっと異質なノイズというか、不思議なギターがずっと鳴っているのが今井さんによるものです。町田町蔵(イヌ)さんのようなヴォーカルはさすがにできないなと思っていたので、"今井君、町蔵さんに負けないような変な音出して"って無茶振りでお願いをしたんです(笑)。そしたら、最高なのをやってくれましたよね。変な音をてんこ盛りで持ってきてくれたっていう。
-イヌのアヴァンギャルド性が出てます。
みんながやりたがるものではないかもしれないですけど、これもベースでグイグイいく気持ち良さと、ずっと同じフレーズしか出てこないでトランス感があって。そこらへんもイヌというか、町田町蔵感だなと思いますね。
-町蔵さんがバンドを始めたのが10代の頃ですよね。イヌの音楽は、ひと言で言い表せない、混沌とした得体の知れないものが蠢いている感じがありますね。
ライヴ映像とかも、いろいろ上がっているのを観るとすごいんですよね。何がなんだかわからないというか。とにかくあの当時は、同じことをやろうとしている人がいないんです。今はわりとロック・バンドも横並びで、みんなが同じようなものを求めている感じがあるんですけど。フェス的なノリというのかな。あの当時は、ひとつひとつのバンドが絶対同じことはやらないぞっていう感じがあって。今のバンドほど、みなさん仲いい感じもしないし。
-そうですね、どちらかというと(笑)。
いがみ合ってるような感じもあるので。そういう意味では、そこが良さなんじゃないかなって。自分たちの看板を背負ってやっている、お前らとは違うぞっていうのをみんなで言い合っているというか。たまに行きすぎて殴り合いになってるみたいな(笑)。それが音にも表れているなと思いますね。だからすごくみんな強いし、ひとつひとつのバンドの存在意義がある。代わりがないというかね。そこがパンク・ロックのすごく重要な部分で、自分自身も影響を受けているところかもしれないですね。他と似ていないことが重要だったり、自分や自分の音を追求したり、自分の存在ってなんだ? っていうことをDIYで、自分の手で作り上げていく。当時の時代の流れや空気感もあるんだろうけど、20代だったり、町蔵さんとかは10代で、みんな看板を背負ってやっているというのが、この刺激になっているんじゃないかな。
-その感じって今、うらやましくもありますか。
自分はそれを少しでも体験できて良かったなと思いますね。自分も今でも、他の人と同じものを作ろうと思わないし、作りたくないと思いますしね。そういう意味では、ここらへんの時代の生き残りが今でもちょっといるよという感じですよね(笑)。時代にはそぐわないかもしれないですけど、それはそれで、パンク・ロックとして意味があるなと思うし。
-自分の作品作りとも並行しながらの制作となったようですが、改めてこういうところは自分に影響しているんだなと感じるところも多かったですかね。
そうですね。自分の原点の感じがすごくしますね、フレーズとかもそうだし。今言ったような、思想的な部分や考え、言っちゃえばアーティストとしての哲学みたいなものを思うと、ここで作られてるなというのは感じましたね。融通の利かない感じもそうだろうなとか。
-そうなんですね(笑)。
そうなんです(笑)。いろいろと自分を思い返しましたね。これが原因だなと。
-多感な時期にこうした音楽に触れて、好きなもののベクトルが作られて。それがこうして、そのままアーティストになったということですしね。
そうですね。これがなければ、今の自分の形はないだろうし。音楽をやっていたかもわからないですしね。
-アルバムのアートワークにカセットテープが用いられていますが、当時、このような感じで自分なりのミックステープを作ったりしていたんですか。
アナログとかを全部買い揃えるお金はないので、貸しレコード屋さんに行っていたんですよね。当時、そういうパンク・シーンに強い、1コーナーにパンクが揃っている貸しレコード屋さんがあって。そこでどんどん音を仕入れてというのが基本だったので。なので全部カセットでしたね。このブックレット(初回限定盤に封入)に映っているカセットも、当時の自分のものもあったりするんです。ほとんど残ってなかったんだけど、それでも残っていたもののいくつかで。
-一生懸命、自分でタイトルを書き込んだりしていた時代ですよね。
そうです、これもよく見ると、当時の自分が書いた文字も見えますね(笑)。
-リリース後は、このアルバムでのライヴなども考えているんですか。
こんな感じで、自分が楽しいなと思って作ってきたものなので、全然そこまで考えてないんですよね。実際に歌いながらベースを弾けるかっていう問題も出てくるし。だからやれるのがあればやるかもくらいには思ってます。今年はライヴが少しずつやれるようになってきている状況なので、やっていこうかなというのと。
-今年に入って、ライヴも声出しができるようになってきたりとライヴの状況もどんどん変化してきているので、楽しみでもあります。
そうですね。でもやる側としては、そういうのはあまり関係なく、自分たちのやれるものをやるだけなんで。(声出しでもそうでなくても)どちらでも楽しんでもらうものをやるというだけなんですよね。