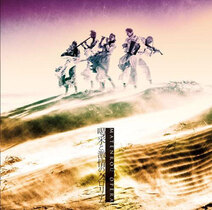INTERVIEW
摩天楼オペラ
2019.02.21UPDATE
2019年02月号掲載
Member:苑(Vo) JaY(Gt) 燿(Ba) 彩雨(Key) 響(Dr)
Interviewer:杉江 由紀
時は来た。今年1月にドラマー、響が正式加入したことで、ついに完全体となった新生摩天楼オペラがここから大きく動き出す。そして、その大事なタイミングで発表される今回のフル・アルバム『Human Dignity』は、"人間の尊厳"をテーマに構成されたフル・ボリュームの大充実な力作に他ならない。結成以来、12年をかけて積み上げてきた摩天楼オペラとしてのアイデンティティを基盤にしつつも、新たな体制になったことにより生まれた今までにはないアプローチや、斬新な発想を貪欲に取り込みながら仕上げられた今作は、摩天楼オペラならではのものであると同時に、以前の摩天楼オペラでは成し得なかったことも具現化した1枚だと言えよう。
-今年の元旦に、もともとサポートとして参加されていたドラマー、響さんを正式メンバーとして迎えられたそうですね。今回のアルバム『Human Dignity』は、新たな5人体制となってから初めての作品ということになりますが、やはりその事実はかなり音に反映される形となったようですね。
苑:このアルバムは作曲段階から響が入って5人で作ったんです。やっぱりメンバーとして、ドラマーがいるかいないかの違いは曲を作っていくうえでかなり大きかったですね。というのも、僕らはセッションみたいに"せーの"で曲をスタジオで作ることも多いから。ある意味とても作りやすかったし、みんなでそうやって一緒に曲を作れることが本当に楽しかったです。
-響さんにとってはメンバーとして初のアルバム制作になったわけですが、ご自身がこのバンドの一員として担っていくべきことは、どんなことだと認識されていましたか?
響:ドラマーやドラム経験のある人間が考えるリズム・パターンとかフィルとかと、ドラマー以外の人が考えるそれっていうのは、根本的に違うところがどうしても多いと思うんですよ。作品としてできあがってしまえば聴く側はさほど感じないのかもしれないですけど、僕含めドラマーからすると"あ、これはドラマーが作ったフレーズじゃないな"って意外とすぐわかるんですね。"いやいや、これは手が3本ないとできないでしょ"みたいなのってありますからね(笑)。
-昨今そのあたりは、レコーディングでも打ち込みを駆使することで具現化しているパターンも増えているように感じます。
響:そういう意味でも、今回はちゃんとドラマーとして作った音やフレーズをそれぞれの曲に対してしっかり当てはめていこうと思っていたんです。ただ、僕はもともとヴィジュアル系のフィールドでやっていたわけではなかったんですね。いわゆるメタルコアをずっとやってきたなかで、去年のシングル『Invisible Chaos』(2018年6月リリース)の制作からサポート参加をするようになったんですよ。「Invisible Chaos」はラウド寄りな曲だったとはいえ、カップリングの2曲は結構ポップな感じだったので、今まであまりやったことがなかったですし、『喝采と激情のグロリア』(2013年リリースのアルバム)あたりからのメロスピ的な曲を聴いてきた身としては、想像していなかったような曲が出てきたという感じで(笑)、新しい世界に慣れていくのに最初はちょっと戸惑いがあったのも事実です。でも、今回はそれから少し時間も経ってのアルバム制作だったのと、基本的には『Invisible Chaos』からの流れを継いだ内容になっているのもあって、思っていたよりはスムーズにレコーディングできた気がします。
-ちなみに、摩天楼オペラではセッションで作っていく楽曲も多いとのことですが、今作において最も制作初期にできあがったのはどの曲だったのかも知りたいです。
苑:1曲目の「Human Dignity」です。JaYが"こんなリフできました"って言い出した時点から"これこれ! 次欲しいのはこういうのだよ"と思って(笑)。これに僕が歌メロをつけたら、間違いなく新しい摩天楼オペラが生まれるなという確信があったんです。だから、今回はこの曲を軸にアルバムを作っていくことになりました。
-当初、JaYさんはどんなことをイメージしながらそのギター・リフを作られたのですか?
JaY:アルバムの1曲目にくるとしたら、こういう雰囲気がいいなと思いながら作ったんですよね。僕も摩天楼オペラには途中から入っている人間ですけど、これまでの作品って絶対に最初はSEというかインストで始まってるんですよ。今回はそこをいい意味で裏切る形にしたくて、いきなりギターからバーン! って入っていったら面白いんじゃないかと考えたのがこれでした。
-まさに新たな摩天楼オペラの幕開けを飾るのに相応しい楽曲に仕上がっている印象です。なお、こちらの楽曲の作曲クレジット自体はJaYさんと苑さんの連名となっておりますが、原形からこの完成形へと導いていくなかで、各メンバーはどのようなアプローチをしていったことになりますか?
燿:自分的には今までやってきた方法と変わらなかったです。みんなで構成を練ってできたものに対してベース・アレンジをしていきました。今までと違うところがあるとすれば、そこは何よりもメンバーが違うというところでしょうね。響君はもちろん、JaY君にとってもこのアルバムはメンバーになって初めての作品になるだけに、いつも以上にちゃんと弾かなきゃなという気持ちはありました。
-燿さんにとって、新たなリズム隊の相方である響さんはどのような存在感を持った方なのでしょうか?
燿:響君に関しては、サポートで入ってきてくれたときからあまり意識する必要がなかったんですよね。とにかく彼、すごいんですよ(笑)。-そのすごさを、もう少し具体的に解説していただけると嬉しいです。
燿:プレイもですけど、響君はめちゃめちゃ考えるタイプなんです。彼がドラムを叩いているのを聴くと、1回耳にしただけで"あぁ、こう考えてるんだな"ということがすぐわかるので、アクセントをどこにつけたいのか、どういうグルーヴにしたいのかがすごく掴みやすかったんですよ。フィルの入れ方とかも、細かく考えたうえで入れているんだなということが伝わってくる音になっているので、本当にやりやすかったですね。
響:僕、絶対に譜面を作るんですよ。どんな簡単な曲でも全曲。こうしたいな、こういうフレーズがいいなと思ったらまずは譜面に起こすし、ライヴでもできるだけそれを忠実に再現したいんです。単純に神経質なだけなんでしょうけどね(笑)。
苑:そういうところは、響とJaYは正反対なんですよね(笑)。響は理論派だし、JaYは感覚派なんですよ。