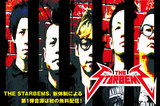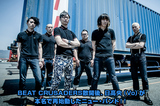COLUMN
THE STARBEMS 日高 央の激トーク!! 第七回
日高:もしかしたら、今いじめられっ子で自分が学校や社会にフィットしないと思っている子は、ふみおさんのストーリーがヒントになるかもしれないですよね。たぶんKEMURIが歌ってきたことってそういうことだとも思うし。
伊藤:絶対にそうだと思う。マイノリティはマイノリティだったよね。人間は、そのマイノリティの中でも、マジョリティとマイノリティを作るでしょ。人は優越感なしには存在できないからね。そういうことで言うと、マイナー男子みたいな気持ちはすごくわかる(笑)。当時、"あれ、俺の話いまひとつ通じてないな"っていうことがあったから。だからほんとに、テレビをつけると心が痛いニュースがあるよね。
日高:殺人か自殺のニュースは、ほぼ毎日ですからね。KEMURIの独自性って何だろうって思ったとき、楽曲にふみおさんの疎外感とか孤独とかが集約されているところなのかなと。
伊藤:ありがとうございます。
日高:津田(紀昭/Ba)さんと一緒にやっているのもデカいんでしょうね。津田さんももしかしたら同じタイプなのかなって、あの人も変わった人じゃないですか(笑)。
伊藤:みんな似たもの同士だと思うよ。バンドやるやつなんてね。
日高:どこかでフィットしないなっていうのを、無理くり合わせていて、その快感もあったりするし。
伊藤:結局似た者同士は仲良くなるんだなと思った話で、この間名古屋でライヴをしたとき、the 原爆オナニーズのTAYLOWさんが観に来てくれて。ずいぶん久しぶりお会いしたんですよ。KEMURIが解散する前に一度だけ対バンさせていただいたことがあって。ひとしきりバンドを見て、KEMURIのライヴが終わってから話していたんですけど。"TAYLOWさん昔はどんなだったんですか?"って訊いたら、"いやあ、大変だったよ。横山とかがライヴ終わったあと殴り込みに来てさ"とか――。
日高:健じゃなくて、G.I.S.Mの横山さんね。
伊藤:そうそう(笑)。でもそのあとすごく仲良くなったとか、いろんな話聴いて。やっぱり似た者同士だったんですねって話をしてたんですよね。
日高:TAYLOWさんもたしか、Sid Viciousに会いたくて何も考えずにイギリスにいって、あの人たぶん、唯一Sidを見ている日本人なんですよね。
伊藤:そう、しかも唯一1980年にTHE SPECIALSのライヴをロンドンで観ている。
日高:すごくマニアックですよ。
-いろんなバンドの話が出てきて歴史の話でも聞いているみたいです(笑)。
日高:こういう20周年をコンパイルした本とか出しましょうよ。さっきのロードランナーの件とかもっと精密なもの聴きたいファン結構いると思いますよ。
伊藤:いやたぶん、読まなきゃよかったって思うよ(笑)。俺、結構アーティスト本読むんだけどさ。夢だけ見ておきたかったなっていうのも多いよね。
-でもアーティスト本って、裏側にあったものを知るのが楽しくて。この時代はこんなだったとか、このアルバムの背景はこんなだったとかが面白いじゃないですか。
 伊藤:うん。たしかに、面白いよね。以前、 Bill Stevenson(DESCENDENTS/ALL)のところでレコーディングしてるときに、BLACK FLAGのオリジナル・ギタリストの、Chuck Dukowskiが来ていて当時の話を訊いたんだけど。インターネットがない80年代に、西海岸のバンドが、どうやって東海岸にライヴに行ったのかっていったら、まず中西部に行ったっていうんだよね。それは、ファンジン繋がりで電話をして、"今度行くんだけど、宣伝してくれるか"って。それでファンジン作っているやつが、今度BLACK FLAGがくるって宣伝をして。あっという間にそれが広がって、東海岸でも人気が出ていくっていう。でも東海岸のシーンは当時から、西海岸とは全然違っていたみたいで。
伊藤:うん。たしかに、面白いよね。以前、 Bill Stevenson(DESCENDENTS/ALL)のところでレコーディングしてるときに、BLACK FLAGのオリジナル・ギタリストの、Chuck Dukowskiが来ていて当時の話を訊いたんだけど。インターネットがない80年代に、西海岸のバンドが、どうやって東海岸にライヴに行ったのかっていったら、まず中西部に行ったっていうんだよね。それは、ファンジン繋がりで電話をして、"今度行くんだけど、宣伝してくれるか"って。それでファンジン作っているやつが、今度BLACK FLAGがくるって宣伝をして。あっという間にそれが広がって、東海岸でも人気が出ていくっていう。でも東海岸のシーンは当時から、西海岸とは全然違っていたみたいで。
日高:MINOR THREAT的な、ストイックな感じのバンドが多かったりしましたね。
伊藤:バンド同士は仲良くなっていったんだけど、段々とライヴが激しくて、みんなめちゃめちゃ暴れているという噂になって、じゃあ俺たちも腕試しをしに行こうって、高校で運動をやっているようなやつが入ってきて、もともといるスケーターとか客との衝突がはじまって。どんどんバイオレンスな方向に繋がってシーン自体がダメになっちゃったんだって。そういういろんな話を訊くと、面白いよね。
日高:意外と、各シーンっていうのは短いんですよね、ニューヨーク・ハードコアも2年くらいで終わっていたりとか。LAもそう。OPERATION IVYに至っては、あっという間に終わったし。で、そこにどんどん尾ひれがつくというか。でもみんな、フィットしないものをなんとかしようとあがいていた、強烈な証なんでしょうね。
伊藤:それは、こういうジャンルの特有ものだと思うからね。でも普遍的なものはあるんじゃないかなという気がしますね。
日高:今日の話の中にヒントは転がっている気はしますね。だから、KEMURIのライヴを見ていても、きっと今のお客さんはふみおさんをはみ出しているとは思ってなかったと思うんですけど、我々としてはその気持ちはずっと続いているんですよね。未だに、フィットしないなっていう。音楽界でもフィットしてないし(笑)。
伊藤:あまのじゃく体質なんだよね。
日高:それがパンクの魅力だったりもしただろうし。この世代のスタートはそこだと思う。観てたパンクスたちは、ひとつひとつ違うっていうか。LAUGHIN'NOSEもいればTHE WILLARDもいて、SODOMもいて、AUTO-MODもいて。その百花繚乱にどんどん惹かれていくというか。自分がどこにはまるのか、ライヴに行くたびにワクワクしちゃうというかね。
-THE STARBEMSのメンバーもあまのじゃくというのは通じるものがありますか。
日高:うちのギターの越川(和磨)なんかもだいぶ破天荒なやつですからね。
伊藤:面白いよね。
日高:こないだもサンダルでライヴやるっていうから大丈夫かって言ったら、結局裸足になっていたり(笑)。黒霧島とかがアンプの上に置いてある日もあるし。いつの間に飲んでたんだ!?っていう。そのくらい、フィットしなくてもいいんだなっていうのは、今日の話で腑に落ちた。
伊藤:それを突き詰めてもらうしかないんだよね。
日高:そうなんですよね。2000年代くらいってもしかしたらみんながみんな、わりと型にはまって、ちゃんとバンドやろうみたいな時期もあったと思うんですけど。今は、好きにやろうっていうのでいいのかもしれない。
伊藤:すべて、怒りも喜びも、音楽に向けるというのがいいかなって思う。
日高:会社と一緒で、そこを人間関係にぶつけても実は解決しないっていうかね。人間同士の軋轢を解決するのは時間しかないというか。だったら、自分の与えられた仕事を黙々とやるとか、それで協力しあった方が解決が早いのかなっていうね。
伊藤:大人だな、日高君。
日高:いやいや、ふみおさんと話しているといろんなことが腑に落ちるんですよ。ほんと、ロードランナー行ってみます(笑)。
【日高 央の1枚】
THE SPECIALS
『Specials』
(1979)
【伊藤ふみおの1枚】
STIFF LITTLE FINGERS
『Inflammable Material』
(1979)













![[MVフル] THE STARBEMS「Vanishing City」](https://i.ytimg.com/vi/8lbgDVxttf0/hqdefault.jpg)