INTERVIEW
DREAM THEATER
2025.02.07UPDATE
2025年02月号掲載
Member:James LaBrie(Vo)
Interviewer:菅谷 透 Translator:安江 幸子
俺が思うに、DTが100パーセント責任を持って言えることの1つは、アルバムを出すごとに成長を実感できていることじゃないかな
-個人的には、Mike Mangini在籍時のアルバムはどちらかと言えばハード・ロックのバックボーンを感じることが多かったのですが、今回はメタルの側面が強く表れているように感じました。過去にPortnoyが在籍していた時期も『Train Of Thought』(2003年リリースの7thアルバム)等メタリックなアルバムがありましたが、やはり彼の影響が大きいのでしょうか?
サウンドに影響を与えたのは間違いないね。さっきも言ったけどあいつはソングライティングにも参加していたし、そのことが方向性や全体の雰囲気に影響を与えたんだ。あいつは昔からメタルヘッドだったから、アグレッシヴでヘヴィな音楽が好きだしね。同時に、初めからプログレをこよなく愛してきたんだ。それだけでなく本当にたくさんのタイプの音楽に対する審美眼があるから......俺たちは全員そうだね。だからこそDTの音楽はとても折衷的で多彩なんだ。ただ、君たちが今回のアルバムにヘヴィな要素を強く感じているのは、歌詞の内容もあるんじゃないかな。このアルバムはコンセプト・アルバムではなくて、テーマに基づいたアルバムと言ったほうが合っている。歌詞はみんな"パラソムニア"(睡眠時随伴症)のことを言っているんだ。パラソムニアというのはとても不吉で、ダークで、心をかき乱すし、現実世界から切り離されるし、怖いし......そんな題材だよ。歌詞がそういう感じだから、音楽にもそれを反映させないといけない。その唯一の方法は、そういった要素を感じさせる音楽を作ることなんだ。ダークさがあって、ヘヴィで、周りから隔離されたような、途方に暮れたような、怖い気分になるものをね。困惑して、圧倒されて、抑圧されて。そういう感情全てを音楽的にも感じられるようにすることで、とても不穏で落ち着かない歌詞をサポートするんだ。狙いは的中できたと思うね。(歌詞と音楽の)一体感があるし、素晴らしい融合だと思う。そうあるべきなんだ。そうでないと核心を失って、気の抜けた、混乱しかないアルバムになってしまう。そうなったら絶対に上手くいかない。
-ということは初めにパラソムニアを題材にするという考えがあって、それに合った音楽を作っていったのだと思いますが、目指す音楽性があったのでしょうか。
そうだね。歌詞の内容がパラソムニアになることは分かっていたんだ。それが音楽的な方向性の原動力になったのは間違いないね。一旦このことについて考え始めると......パラソムニアとは何を意味するのかを考え始めて、その意味を自分のものとして吸収できると、自分がその導管になる。自分の中から流れ出てくるんだ。アイディアがあって、アイディアの種があって、そこから始まる。さっき話したけど「Night Terror」ができたときは、これこそ俺たちの狙いが形になっているという手応えがあったんだ。それが次の曲に影響を与えて、その次の曲、そのまた次の曲......と波及していった。自分の中で全てが展開するのをゆったりじっくりと待つ感じだね。そうしたらそれを活かしたり掘り下げたりすることができるようになる。そして熱情的で真摯なものができあがるんだ。
-だからこそ、コンセプト・アルバムではなくとも一貫した筋のようなものを感じ取ることができるのですね。
そうだね。
-アートワークでは夢遊病の女性とベッドが描かれており、『Images And Words』と関連しているのではないかという声も見られました。『Images And Words』は女性というより女の子ですね。
そう、女の子だ。実は10年くらい前に本人と対面したんだ。俺たちのショーに来てくれてね。もう大人だったよ、女の子じゃなくて(笑)。
-そうなんですね!
ああ! 対面できて最高だったよ。もともと面識はなかったけど、わざわざ自己紹介しに俺たちのところに来てくれたんだ。(※笑顔で)びっくりしたよ! 思わず"なんだって? 君が『Images And Words』のあの女の子なのかい? マジか!"と言ってしまったけど(笑)、あれはクールな体験だった。俺たちもできあがった今回のアートワークを見て"!"と思ったよ。今回もHugh Symeが手掛けてくれてね(※『Images And Words』のアートワークを手掛けたのはLarry Freemantle)。ものすごく才能がある人で、俺たちも長年仕事を共にしているんだ。今回はブックレット全体を通じて"『Images And Words』に雰囲気が似ているな"と思える箇所があった。でもそれは単にHughの表現がそんな感じだっただけなんだ。意図してやったとか、そういうことでは全くなくてね。後になって比較したり、DTの過去のアルバムにあったものと似た要素を見いだしたりするのは簡単だけど。......だから偶然ではあるけど、本当に偶然だったのかと思ったりもするよね。DTのアルバムだし、こういう音楽だし、自分にこういうふうに訴え掛けてくる内容だし、こういうアートワークになるべくしてなったというのはある。俺たちがイメージについて感じていることは知らせておくけど、具体的にどういうものにするのかは、アーティストとしての彼の自由意思に任せているんだ。で、いつもぴったりのものを作ってくれている気がするよ。俺たちに言わせれば彼は驚く程イマジネーションが豊かで、その芸術性が全てを物語っているんだ。
-ちなみに彼はデザインする前に曲を聴いているのでしょうか。
彼は何よりも歌詞を優先して知りたがるね。歌詞を手に入れるとそれをじっくり読み通して、語り掛けてくるものから多くのインスピレーションを得るんだ。そしてできるときは......俺たちが曲を作る段階にいるときは、曲を聴くこともある。一部だけとかね。でもたいていの場合、RUSHのときもそうだったけど(※SymeはRUSHの作品を多く手掛けたことでも知られる)、彼の主なインスピレーションは歌詞なんだ。そこからヴィジュアル的な表現を決めていく。
-一緒に仕事をしてきた時期も長いですし、少ない要素でも具体的な図を描くことができているんですね。
ああ。俺たちが何を望まないかもちゃんと分かってくれているよ(笑)。個人的にも親しいし、これだけ長い間一緒にやっていると、声に出さない言葉で通じ合っているようなものなんだ。どこに向かいたいかもなんとなく分かる。
-さて、いくつか曲についても質問させてください。「In The Arms Of Morpheus」はストーリー性を感じさせるSEも盛り込まれたインスト・ナンバーで、この先の展開に期待が高まる曲ですね。
ああ、テーマだからね。
-個人的にはアルバムの導入として『Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory』や、『Black Clouds & Silver Linings』の「A Nightmare To Remember」のような印象も受けました。
この曲はライティング過程の後のほうでできたんだ。他の曲がすでに書かれた後だったから、他の曲の音楽的なテーマやメロディを盛り込むことができた。それで、どこかの段階で、"他の曲の要素を盛り込んだ曲でアルバムを始めることができたらいいんじゃないか"という話になったんだ。この先音楽的にどうなるかの予示みたいな感じでね。この後に出てくる曲のテーマが一部織り込まれている。それでアルバムを聴き進むにつれてそのテーマが出てきて、"あぁ、あれか"と思える効果があるんだ。映画が始まる前にちょっと飛ばしで観て、後で起こることを先に観るような感じだな。で、初めに戻って、今度は自然な展開に任せるんだ。この手のアルバムのセットアップとして美しい手法だね。確かに他のコンセプト作品に似ていると言えるけど......コンセプト・アルバムと考えやすい内容ではあるけど、実際は違う。テーマ的なアルバムなんだ。
-先程話に出てきた「Night Terror」は第1弾シングルでしたね。"Portnoyが帰ってきた!"というインパクトを与える楽曲で、過去の楽曲と通ずる部分もありながら新鮮さもあるナンバーです。
そうだね。どこかの時点で話し合っていたんだが、俺たちに起こったことが別の部分に起因しているのであれば、もしああいうことが起こらなかったら......俺たちがどんな人間なのかを強烈に示す曲ができなかったら、このバンドが期待されるものを生み出すことができなかったら、それはバンドにとって恐怖だと。もし俺たちが、自分たちを自分たちならしめていたものを掘り下げることができなかったらね。「Night Terror」のような曲をとってみても――今はアルバム全体を聴くことができるわけだけど、全てはケミストリー次第なんだ。何人かが一堂に会するとき、何が自分を作り上げてきたのか、何が自分のサウンドを作り上げてきたのか、何年もの間何を手に入れることができたのかを考えるわけだけど――ほら、世の中には"DTに影響を受けてきました。僕たちはDTみたいなサウンドです"なんてバンドがたくさんあるだろう? そういうバンドの曲を聴いてみると、確かに断片から"あぁ、これはプログレだな"とか"プログレ要素のあるメタルだな"等と分かるよね。DTの場合、この『Parasomnia』というアルバムでは、俺たちにアイデンティティを与えている要素はなくなることがないと思えるんだ。そして遅かれ早かれ、他のアルバムと一体化していく。と言っても願わくは、その(昔ながらの)要素があってもフレッシュなものを作っていきたいけどね。俺が思うに、DTが100パーセント責任を持って言えることの1つは、アルバムを出すごとに成長を実感できていることじゃないかな。ちょっと回りくどい言い方になるけど、どのアルバムも俺には水晶玉のように見えるんだ。つまり、その特定の時期に俺たちの住む世界で起こっていたことが見えるということだね。俺たち個人や、バンドという集合体としての世界が、社会的にも政治的にも感情的にも影響を与えている。全てのものには収まるべきところがあるんだ。俺たちは自分たちがどこに向かうべきか、音楽的に何をする必要があるかについて、常にものすごく強く意識している。"これはプログレのモンスターになるぞ"、"壮大なロック・オペラだ"なんて謳い文句を言っていたとしても、これがそのときの俺たちが行くべき道だという確信があって、アイデンティティを失うこともない。もし『Parasomnia』とか、「Night Terror」のような曲をやるとしても、それは自然な展開でそうなるものなんだ。5人のメンバーという要素があって、コミュニケーションを交わし合って、アイディアを投げ合っている。その影響元はいつだって、俺たちを俺たちならしめてきたものなんだ。俺たちは本当にたくさんのアーティストたちから影響を受けて育ってきた。その影響を遅かれ早かれ自分のものにして、自然に自分の一部にすると、自分の感じているものを独特の形で伝えることができるようになる。どんなアーティストでも同じだと思うけどね。
-今のお話を聴いていると、「Night Terror」は第1弾シングルになるべくしてなったような気がします。
まぁ、そうだね。いくつか候補にしていた曲はあったけど。レーベルに「Midnight Messiah」はどうかとか、別の人に"そうかな?「A Broken Man」のほうがいいんじゃないか? DTらしい激しさと美しさがある"なんて言われたりした。俺自身はJohn Petrucciとの会話の中で再三「Night Terror」に言及していたのを思い出すけどね。"「Night Terror」だ! 開けた感じになるし、ヘヴィだし、とてもメロディックで、1回聴いたら覚えられる"と言っていたんだ。それでいてDTの実力を見せつけられる曲だからね。強力でパワフルだし、ヘヴィで、プログレらしさを全て兼ね備えている。テクニカルな曲でもある。Johnも"そうだな、100パーセント同意するよ"と言ってくれた。ともあれ、話し合いを何度も重ねて、最終的に「Night Terror」を最初のシングルにしたんだ。どんなアルバムでも、1stシングルはリスナーが他の曲を聴く機会ができたときにその導入ができるかどうかを考えなければならない。曲同士の兼ね合いもね。これから起こることを予示する曲は何かを考えるんだ。
-「A Broken Man」は緊迫感のある進行ですが、ジャジーなセクションも設けられている等、ユニークな楽曲になっています。
(笑)あのジャジーなセクションについては、メンバーに"これはないよ"と言ったのを覚えているよ(苦笑)。"ノー、俺には良さが感じられない"ってね。そうしたら"いや、ちょっと時間をかけて吟味しないとダメだろ"と言われて。"分かったよ......ちょっと内容をじっくり検討してみる"と返して、よく聴いてみると"あぁ、なるほど"と分かったんだ。これも真のDT的な曲だね。"ジャーン!"という感じで、"まさかここへ来てジャズ・クラブに足を踏み入れるなんて思わなかっただろ?"と訴え掛けてくるんだ。トリッキーな曲だよ。ヘヴィで、初っ端から真のDTらしさが全開になっている。それが突然あんな感じの優美な曲になるんだから。そして手強くもある。手強くて、耳に残って......「A Broken Man」のような曲の魅力はそういうところにあると思うね。歌詞はパラソムニアのテーマに沿ったものになっている。――一つ一つの曲について聞かれると、ある意味答えるのが難しいことがあるんだ。というのも、感性で作っているところがあるからね。"この曲ではこっち方面に展開するのがいいかもしれない。こういう要素があるから。どう思う?"なんて話はするけど、全てのステップを乗り切ることができるのは、絶え間ないコミュニケーションの賜物なんだ。俺にとっては、特定の曲の話をすると、"こういう会話をしたしこういう展開をしたけど、それは何年もやってきたことだからなぁ"と思ってしまうんだ。壊れていないものを直す必要はないから続けてきたまでで、俺たちにとってはどうやらそのやり方が上手くいくらしい。それからもう1つ、音楽のことをじっくり考えてみると、なかなか奇妙な話だよ。何もないところから引っ張ってくるものだと思うのは馬鹿げている。そりゃ"自分の内面から出てくるものだ"と言うことはできるけど、それは経験だったり、知識だったり、楽器との関係性だったり、その曲の在り方をどう認識しているかも関係してくるからね。そういうものは自分の内面を強く掘り下げることによってしっかりと引っ張り出せる。そしてその作業はコンスタントに行われているんだ。でもいざ分析するとなると、5人の異なる人間から来るものだし、インスピレーション、気分、考えから来ている。それらが1つになって、パワフルに心を動かせる、心に訴え掛けられているのは素晴らしいことだ。
-自然の流れで生まれるものもあるでしょうから、それを言語化してくれと言うのは不適切なのかもしれませんが、引き続き質問させてください。この曲は退役軍人のPTSDをテーマにしているのですよね?
正しいよ。
















































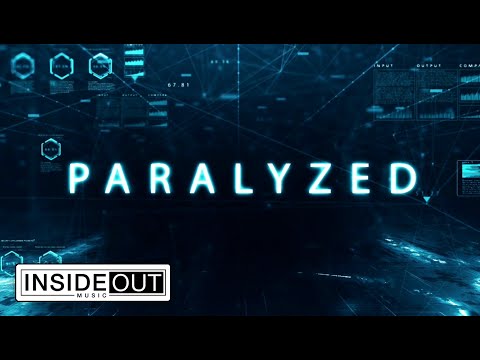


![Dream Theater – Our New World [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/JnLdx2FyNqg/hqdefault.jpg)
![Dream Theater - The Gift Of Music [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/fae4FQ4McSY/hqdefault.jpg)

![Dream Theater - The Looking Glass [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/4Cf1CF6Avvc/hqdefault.jpg)
![Dream Theater - The Enemy Inside [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/0clL8QLQsrc/hqdefault.jpg)
![Dream Theater - On The Backs Of Angels [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/oTJRivZTMLs/hqdefault.jpg)
![Dream Theater - A Rite Of Passage [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/xg4eAv63BXQ/hqdefault.jpg)
![Dream Theater - Wither [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/-boKk8uhmcY/hqdefault.jpg)
![Dream Theater - Forsaken [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/dRBP1rpE5y8/hqdefault.jpg)
![Dream Theater - Constant Motion [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/RFiexmXEccE/hqdefault.jpg)
![Dream Theater - Hollow Years [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/IgU-0__fpXY/hqdefault.jpg)
![Dream Theater - The Silent Man [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/M1gFXVANCt8/hqdefault.jpg)
![Dream Theater - Lie [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/VD7OdyY1js4/hqdefault.jpg)
![Dream Theater - Take The Time [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/C5sg8heGdyk/hqdefault.jpg)
![Dream Theater - Another Day [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/LYtiDCXLAcQ/hqdefault.jpg)
![Dream Theater - Pull Me Under [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/mipc-JxrhRk/hqdefault.jpg)







