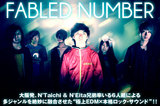INTERVIEW
FABLED NUMBER
2014.07.11UPDATE
2014年07月号掲載
Member:N'Eita (Gt/Vo) Mako-Albert (Gt) N'Taichi (Ba/Cho) Mr.Donuld Betch (Dr)
Chii,lulupucchi (Key/Per) Ikki-Rodriguez (Samp/Prog)
Interviewer:山口 智男
-ノレるってことはこのバンドにとって重要ですか?
N'Taichi:1番大事ですね。そこにリズムがあって、ヴォーカルだけでもノレるんですよ。言ってしまえば。
N'Eita:そういう意味では、どんな音を出してるかはそんなに関係ないかもしれない。今だったら電子音がしっかり鳴っているけど、それも今後、変わるかもしれない。出せる音の幅はメンバーそれぞれが鍛えて、広げていったらいいんですけど、基本的にビートを感じて、その中でノリを崩さず、しっかり歌を入れていこうというコンセプトだけはしっかりと持っていきたいんです。音色は変わっても、FABLED NUMBERは変わらんよなっていうのが絶対にある。たとえば、今、キーボードで弾いてるフレーズがギターやホーンになっても、ビート感とヴォーカルが変わらなければ、FABLED NUMBERらしいものになると思うんですよ。
N'Taichi:とにかく人をノセてアゲたい。それが根底にあるんですけど、バラードもやりますし、俺たちのビート・メロディで胸が熱くなったり切なくなったりして涙や感動してもらえたら、それが最高なんです。
-ところで、みなさん日本人離れしたお名前をお持ちですね(笑)。
N'Eita:最初にBetch君が来たとき、ベッチン、ベッチンって言ってたんですけど、なんかベッチンじゃ彼のすべてを表現できないと思ったんですよね。
N'Taichi:ベッチンって地元の先輩みたいじゃないですか。そんなんじゃ、彼のなりを言い表せない。
N'Eita:まずミスターはつけないと。
N'Taichi:ミスターは絶対だね。
N'Eita:それでなんとなくドナルドダックとマクドナルドを合わせて、Mr. Donuld Betch。うわ、メッチャしっくり来るわって(笑)。最初、彼だけやったんですけど、Chiiちゃんももうちょっとなんか欲しいな。
N'Taichi:字体の長さ的にも後に何か欲しいってことで、EMILIO PUCCIって高級ブランドがあるから。
N'Eita:いや、言ったら、飼ってる猫の名前を2つつけただけなんです。luluとpucchiを。それでChii,lulupucchi。1人と2匹みたいな(笑)。じゃあ、この際、N'TaichiとN'Eitaは兄弟とわかるようにいじらんと、それ以外はこれから入ってくる奴らも変な名前をつけようってなって。
-そういうところも含めて1つの世界観を打ち出していると?
N'Taichi:そうですそうです。
N'Eita:良く取ってもらえるなら。
Betch:楽しいバンドです(笑)。
-これが自分たちの音だと言える作品になった前作『Might makes right』をリリースして、どんな手応えが得られましたか?
N'Taichi:前作に至るまでけっこう期間があいとって、その前作よりも前の作品『Fisherman's Profit』は11曲入りのフル・アルバムで、自主制作で出したんですよ。それもまた全然音楽性が違って、そこから去年出した前作に至るまでに音楽性の変化がすごいあって、そこでこういうアプローチで行こうぜってN'Eitaと決めたんですけど、それがちゃんと形にできたと思うんですよ。前作ができた時に、こりゃええのができた。絶対イケるって思いましたね。
N'Eita:初めて全国に流通するということで、自分らで考えて、こういうコンセプトだってことを言葉にしたんですけど、俺たちのことを、みんなは聴いてどんなふうに判断するんだろうとか、それを売るお店の人はどういう言葉で表現するんだろうとかって思ってたんですけど、実際の反応として返ってきたのは、その幅がこっちからこっちまで僕らが思っていた以上に広くてうれしかったですね。サカナクション好きは必聴!ってコメントが書かれてたり、ギター・ロック・バンドが並んでる中に僕らが入ってたり、THREE LIGHTS DOWN KINGSとかFear, and Loathing in Las Vegasとかと僕らが並んでたり、電子音で捉える人もおれば、ギター中心で捉える人もおって、このひと括りとされず、大きく捉えられてもらえたのがよかったです。
N'Taichi:普遍的なものでありたいんですよね。
N'Eita:いろいろなところにツアーで行ったんですけど、CDをしっかり聴いて予習してきてくれた人が多かったんですよ。これまでもノッてくれる人は多かったですけどね。歌ってる人もおれば、踊ってる人もおる。そういうライヴの感じを見ても、狙いどおりやったかな。しっかり歌も聴いてくれてるんや、ビートも感じてくれてるんやっていうのがわかってよかったです。それを踏まえたうえで、今回はもう1歩踏み込んで聴かせられるものにしたいと考えられたんで、前作ではかなり前進させてもらいました。