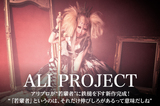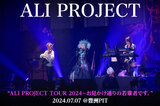INTERVIEW
ALI PROJECT
2025.10.14UPDATE
2025年10月号掲載
Member:宝野 アリカ(Vo) 片倉 三起也(Key)
Interviewer:杉江 由紀
アングラならではの醍醐味を堪能せよ。"Underground Insanity"と冠されたALI PROJECTの最新アルバムは、鬼才 片倉三起也の生み出す色とりどりな楽曲たちと、宝野アリカ様の描かれる忌憚なく容赦もない素晴らしき歌詞たち、そして千変万化する表情豊かな歌によって織り上げられた逸品となる。凛々しきリード・チューン「日本男子、獅子奮迅」を筆頭に、暗いカオス感の漂う「地下牢(ダンジョン)から愛を込めて」のような楽曲まで、その階層は実に深い。
-ALI PROJECTは毎作コンセプチュアルな世界を提示しており、近年ですと『天気晴朗ナレドモ波高シ』(2023年リリースのアルバム)では、日露戦争をモチーフにしながら、現代の"戦争と平和"について描かれていらっしゃいましたし、前作『若輩者』(2024年リリースのアルバム)では、圧倒的なラスボス感を漂わせる一方で、若気の至りについて秀逸な表現をされていらっしゃいました。今作『Underground Insanity』の方向性については、いつどのようにして定まったものだったのかをまずは教えてください。
片倉:ここまでの流れからいっても、ALI PROJECTの場合は、最初にアルバム・タイトルが決まらないと全体を作っていくことはできないので、僕が曲を書き出したくらいの頃にはまず"Underground"という言葉が浮上してきてました。まぁ、"Underground"というのは散々使い古された言葉だけど、僕はアリプロ(ALI PROJECT)って基本的にアングラな存在だと思ってるので、その点ですごくしっくり来た言葉だったわけです。
宝野:そうそう、まさにアリプロってアングラなんですよ。特に精神的な部分で。
片倉:カウンターカルチャーというよりは、"Underground"のほうがアリプロっぽいもんね。ただ、アルバム・タイトルが単に"Underground"ってなるのはちょっと面白くないので(笑)、もう1つ言葉をそこに組み合わせようということになったんですよ。
宝野:バンド名だとTHE VELVET UNDERGROUNDとかね。そういう雰囲気の言葉を探しながら、最初は"Zealot"っていう単語を組み合わせようかなとしてたんですけど、よくよく調べてみたら実は宗教的な意味合いもあったりするから、ちょっと避けることにしました。で、その後に思い至ったのが2007年に出した『Psychedelic Insanity』っていうアルバムのことだったんですよ。またここで"Insanity"っていう言葉を使うのもアリなんじゃない? と思ったんです。
片倉:ちなみに、あの『Psychedelic Insanity』っていうアルバムは、ALI PROJECTが今のメーカーさんから出すようになって、今までで一番売れた作品なんですよ。そういうげん担ぎもあってこのタイトルにしたところもあります(笑)。
-そんな"Psychedelic Insanity"を踏まえての"Underground Insanity"であるというのは、とても興味深いお話です。と同時に、本作には「ZAZOU通りの猫オンナ」という楽曲が収録されておりまして、これもALI PROJECTが創設したレーベル、ZAZOU RECORDとの関連性を思わせるタイトルでもありますね。
片倉:そこは自然な流れでそうなったっていう感じかな。とはいえ、今回は、結構いろんなことが折り重なりながら『Underground Insanity』ができあがっていったところはあると思います。
-なお、先程は"Underground"という言葉が浮上してきた段階で、片倉さんはすでに曲作りに着手されていたとのお話がありました。今作の中で最初に形となった楽曲は、どちらになるのでしょうか。
片倉:それが、最初のうちは"やわちい"曲しかなかなかできなくて。去年の11月頃にまず出来たのが「Grand Bouquet」だったんですよ。そして、その次にできたのが4分の3拍子のリズムで作った「人形の家」。つまり、いずれも宝野があまり好んでは歌いたがらないタイプの曲が連続してできたことになります(笑)。
宝野:そうね。ふんわりした軽い雰囲気の曲たちではあります。
片倉:テーマ的な部分で"Underground"なところがあるかというと、そこはちょっとまだ定まっていなかったところもありましたね。でも、ある意味ではこの2曲が僕にとってはいいウォーミングアップになったんですよ。
-もっとも、「Grand Bouquet」については、110年もの間フランスの城館内に置き去りにされていたという、オディロン・ルドンによる絵画"グラン・ブーケ"をモチーフに、アリカ様が歌詞を書かれていらっしゃいますので、俗世から隔絶されてしまっていた世界="Underground"として解釈することもできるような気はいたします。
宝野:私としては、とにかく優しい歌詞にしよう、片倉さんが好きな世界にしようということを心掛けながら書きました。早い段階で曲は貰っていたんですけど、この世界を形にするのは少し難しかったですね。だから、順序としてはわりと最後のほうに書くことになってしまいました。
-なんでも、城館内にあった16点の絵画の内15点はフランス国有のオルセー美術館所蔵となったそうで、"グラン・ブーケ"のみが2010年から三菱一号館美術館にて公開されているのだとか。
宝野:その絵たちは本来シリーズ作品みたいになっていて、他は全てパリにあるんですけどね。"グラン・ブーケ"だけは日本で観られるんですよ。
-"グラン・ブーケ"に限らず、ALI PROJECTの音楽世界は文化芸術との繋がりを持つものが少なくありません。今作の「人形の家」は、1800年代後半にヘンリック・イプセンが書いた、同題の戯曲を下敷きにしたものとなりますか?
宝野:もともとこのタイトルにしようと思っていたわけではありませんでした。詞を書いていくうちに途中で"人形の家"と付けたら、イプセンのお話とも通じるような内容になるかな? と思い付いたんですよね。
-しかしながら、この詞はわけあって家出をする主人公側ではなく、"置いていかれた側"の視点で描かれている点が特徴的ですね。
宝野:戯曲のほうは家出をする主人公が、家庭の中で夫に人形扱いをされているみたいな話じゃないですか。この曲の詞に関してはとある女の子が"もうこんな家にいたくない"と都会に家出していって、飼い主? 持ち主? を失ってしまう人形の視点で書いてます。結局、その女の子は都会で自由にいろいろやるんだけど、やっぱりそこでも孤独を感じてしまって家に帰るみたいな流れの話です。曲調はワルツだよね?
片倉:4分の3拍子とかワルツは大体いつもアルバムの中に1曲は入ってるんですけど、今回の「人形の家」は、"宝野さんがワルツを踊るミュージカル"のようなイメージで書いていきたかったんです。僕はアメリカの禁酒法時代とか、あの頃のスタンダード・ジャズが好きでね。ロバート・レッドフォードの出てた映画"華麗なるギャツビー"とか、あとはマリリン・モンローの出てた"お熱いのがお好き"とか、そういった映画のテーマ・ソングや主題歌みたいな感じもちょっと意識してました。
-それから、本作の幕開けを飾るのは、"不思議の国のアリス"を彷彿とさせるような歌詞世界が面白い「Underground Mad Tea Party」ですが、こちらを1曲目に選んだ理由もぜひ教えてください。
片倉:この『Underground Insanity』は全10曲、ボーナス・トラックを入れると11曲ですけど、アルバムの曲順に対する考え方としては昔のアナログLPを意識していたんですよ。つまり、5曲目までがA面で6曲目以降がB面っていうふうにね。なおかつ、A面とB面はそれぞれ異なるテーマでまとめていくという形にしてあります。そうなってくると、A面の1曲目に入れたかったのはとにかく"カッコいい曲"だったんですよ。
宝野:これはいかにもALI PROJECTっぽい感じの曲だよね。歌詞は、まず先にタイトルの"Underground Mad Tea Party"という言葉が思い浮かんだので、そこから広げていきました。ちょうど"Underground"っていうのも入ってるし、今回はこれが1曲目でいいんじゃない? となったんです。内容は地上で戦争が起こってたり、人が死んでいたりするようなときに、地下室でお茶会をしているっていうお話です。
-アリカさんはそれをストーリーテラーの視点で歌われたことになりますか?
宝野:これはお茶会の主催者の視点かな。歌詞の中で具体的に"アリス"っていう言葉は使ってないんだけど、ここでは"あなた"が"アリス"なんです。
-そうした不可思議世界が広がったかと思うと、2曲目に来るのは勇ましき面持ちの「日本男子、獅子奮迅」です。これはALI PROJECTの"大和ソング"シリーズの最新作であると同時に、『Underground Insanity』のリード・チューンともなるそうですが、この楽曲にその大任を任せることになった経緯はどのようなものだったのでしょうか。
宝野:まず、さっき片倉さんの言っていた"A面"のテーマというのは、基本的に勢いのある曲たちを集めたって意味なんですよね。
片倉:そうそう。5曲目までは今回どれもロックだと思ってください。
宝野:だから、曲同士に物語としての繋がりはあまりないんですよ。特に、この曲はアンダーグラウンドとか地下のイメージも関係ないし。だけど、それでも今回「日本男子、獅子奮迅」をリード・チューンにしたのは、強いインパクトを持った曲になったからですね。言いたいことを言い切ってます。
-不協和音を効果的に使われているところも、さすがのALI PROJECTならではです。
片倉:不協和音と面白い転調がいっぱい入ってます。まさに、この曲は、宝野さんがこれまでいろいろ作ってきた"大和ソング"の系列に加わるものとして作りました。
-このたび、アリカ様が「日本男子、獅子奮迅」の歌詞を書かれることになられたきっかけは、何かあったのでしょうか。
宝野:これはともかく、四字熟語の"獅子奮迅"という言葉を使いたかったんです。去年の暮れあたりに佐賀旅行をしたとき、泊まっていたホテルで見かけた中学校の運動部っぽい男の子たちが"獅子奮迅"って書いてあるジャージを着てたんですよね。みんな坊主で細かったから野球部かもしれないし、コーチみたいな人は柔道部っぽい感じもしたんだけど、その書いてあった言葉がとてもカッコいいなと感じてしまって。"よし、次の「大和ソング」ではこれを使おう!"と思ったのがきっかけでした。で、この曲ができてきたときに"おぉ、これだ!"と思ってこの歌詞を乗せていったんです。
-タイトルが"獅子奮迅"だけではなく、"日本男子、獅子奮迅"となっているあたりもポイントですよね。
宝野:それはもう、日本男子に向けて歌ってますから。特に、佐賀で見た少年たちは都会の子たちと違ってすごく純朴な感じがしたんですよ。そのまま清らかなまま、たくましく大きくなっていってほしいなという願いもここには込めてあります。ただ、今の時代って男は男らしくとか、女は女らしくとか、そういうことをあんまり言っちゃいけないみたいな風潮があるじゃない?
-国内外問わずにジェンダーの押し付けはよろしくないという流れになっているところは、あるように思います。"男のくせに"、"女のくせに"等もほぼ禁句となっていますし。けれども、ここでのアリカ様は"母なる優しさと/父なる強さと"という表現をあえて使っていらっしゃるわけですね。
宝野:そういうことです。私はどこかから叩かれるとしても堂々と言いますよ。男は男らしく、女は女らしくでいいじゃないですか。あるいはそういうカテゴリに入りたくないという人がいるなら、ゲイはゲイらしくでいいわけだし。男か女か自分では分からないと言うなら、それもそれでいい。でも女らしくありたい、男らしくありたいっていう人に対してまで、"それはおかしい"という意見が外野から出ることのほうが、よっぽどおかしいんじゃないかしら。
-たしかに。昨今、LGBT界隈では"逆にそんなにLGBTがどうこうとわざわざ騒いでほしくない。放っておいてくれ"という意見が出ているとの話も耳にします。
宝野:自分がどんなふうにありたいかっていうことは大事だけど、他者に対してその人の姿勢を否定するなんて本当におかしい話! そして、誰がなんと言おうと大和魂はこれからも大切にしていきたいです!!
片倉:まぁまぁ、ちょっと落ち着いて(笑)。ちなみに、この歌詞は7月に靖国神社で開催された"みたままつり"の奉納ぼんぼりに書いて納めたんですよ。
宝野:そうそう、刀剣乱舞の絵も一緒に描いてね。「日本男子、獅子奮迅」はちょっと暑苦しいところもある曲なんですけど、これを聴いて日本男子にはすくすくと育っていただきたいなと、私は母のような気持ちでおります。


















![[Official Video] ALI PROJECT - Watashino Barawo Kuminasai - 私の薔薇を喰みなさい](https://i.ytimg.com/vi/CYvCmqpnD3c/hqdefault.jpg)
![[Official Video] ALI PROJECT - Kyomu Densen - 凶夢伝染](https://i.ytimg.com/vi/We_uZ7-_HmM/hqdefault.jpg)
![[Official Video] ALI PROJECT - Jigokuno Mon - 地獄の門](https://i.ytimg.com/vi/z1cAxMLIeaY/hqdefault.jpg)