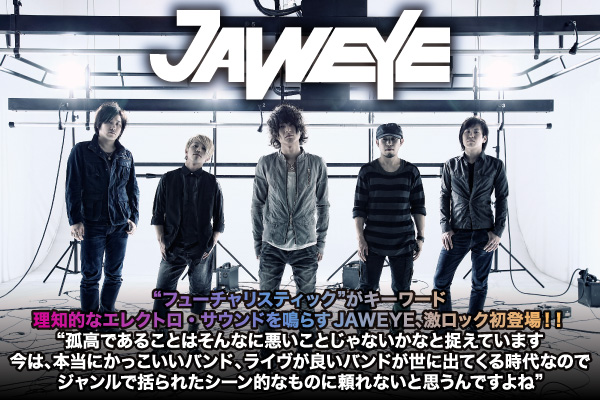INTERVIEW
JAWEYE
2012.08.06UPDATE
2012年08月号掲載
Member:上田 浩平 (Vo/Gt) 師崎 洋平 (Gt)
Interviewer:ムラオカ
-作曲者をみるとJAWEYEとなっていますが、実際曲ができるまでの過程を教えてください。
上田:基本的には僕なり師崎が原型を持ってきて、それを高橋が打ち込んで、師崎を中心にアレンジを組み上げていく、という流れが多いです。JAWEYEが5人になって、制作体制も徐々に慣れてきた感じがあるので、最近はかなりスピード感が出てきました。
-あなたがたの音楽性ですが、ラウドでありながら繊細、肉体的でありながら、知的ですね。他に似たバンドを探してもなかなかいない音楽性だと思います。自分たちの音楽性を言葉で現していただいてもよろしいでしょうか?
上田:なかなか難しいですね......。本当は言葉でバシっと表現ができると、分かりやすいのかもしれないのですが、そうすると、どうしても僕らのいろんな側面が一部だけ強調されてしまうような気がして、どうもしっくりくるのがないんですよね......。逆にいい表現があったら教えて欲しいです(笑)。 個人的には、メロディが良いバンドって言われるのが一番うれしいです。
-音楽性もあってか、あなたがたのファン層はFear, and Loathing in Las Vegasやcoldrainなどのラウドロックのファンと[Champagne]やandropなどの文系ロックのファン層両方が混在しているのが特徴だと思いますが、実際ライヴ会場やSNSなどで見てみていかがでしょうか。
上田:そうですね。対バンなんかもそうなんですが、いろいろなバンドとやらせてもらえてます。幅広い層に聴いてもらえるってことは本当にうれしいです。シーン的なことよりも、ライヴが強いバンド、曲がかっこいいバンドと、並べて聴いてもらえてるってことがありがたいです。
-逆にどちらのシーンにも受け入れられるという可能性もありつつ、どちらのシーンからも浮いてしまうという可能性もあると思いますがいかがですか?
上田:孤高であることはそんなに悪いことじゃないかなと捉えています。今は、本当にかっこいいバンド、ライヴが良いバンドが世に出てくる時代なので、ジャンルで括られたシーン的なものに頼れないと思うんですよね。仲間同士がお互い、1バンドとして屈強になって、音楽性の壁を飛び越えて、一緒にジャンルよりももっと広い意味での、"世代的なシーン"としてみんなを巻き込んでいく、というのが正しいような気がします。僕らもそうありたいですね。
-3曲それぞれを簡単に解説してもらえますか?
上田:Track.1の「STARGAZER」はJAWEYEの持っている武器を全部凝縮した曲だと思っています。踊れるパートもあるし、キャッチーなパートもへヴィなパートもあり、サビもメロディアスですし、"とりあえずこれを聴いておけ!"というJAWEYEが最も得意とするタイプの楽曲だと思いますね。
Track.2の「Plastic Sunlight」はJAWEYEでは初めてツービートを使った曲です。楽曲単体の骨となるアレンジを聴くとメロコアなんですよね。この曲はAメロからサビまで全部良いメロディで繋いだ疾走感のある非常に爽快な曲になっています。
Track.3の「MURAKUMO」という曲は邦ロック的な変化球の曲ですね。サビでガチッとみんなでハンズアップできるパートや掛け合いのパートなどもあって、分かりにくくなり過ぎないように作ってあるので、歌詞の世界観と一緒に楽しんでもらえるような曲になっています。
師崎:和テイストですね。この曲だけタイトルも含めて毛色が違ったものになっています。
-"MURAKUMO"というネーミングにはどういった意味があるのでしょうか?
上田:"月に叢雲(むらくも)花に風"という故事があるんですけど、"叢雲"とは雲の種類で、霞がかる雲のことです。歌詞のストーリーは"どろろ"という漫画の世界観にインスパイアされていて、自分の運命を切り開いていく様を歌詞にしています。"月に叢雲花に風"というのは、名月の夜には叢雲がかかってしまい、満開の花には風が吹いて花が散ってしまうように、うまくいっているように見えても、実はいろんな落とし穴があったり、上手くいっている状態というのは長続きすることはないという意味のことわざです。その言葉を耳にして、"叢雲"ってすごく魅力的なワードだなと思って歌詞に入れてみました。
-最後の質問ですが、シングル・リリースの後にはアルバムも控えていると思うのですが、今後JAWEYEはどういった進化を成し遂げていくのでしょうか?
師崎:とにかくライヴをやっていくしかないですね。こうなりたいなといった漠然としたヴィジョンはありますが、それが確信に変わるのはツアーを回ったりライヴをやっていく中でお客さんの反応を見たりするところに委ねているというところがあって、進化したいからライヴをたくさんやりたいなという感覚はありますね。