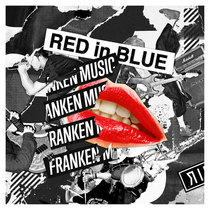INTERVIEW
RED in BLUE
2019.08.20UPDATE
2019年08月号掲載
Member:高橋 祐揮(Vo) 田口 悟(Gt/Cho) 磯村 駿介(Ba/Cho) 山崎 慧(Dr/Cho)
Interviewer:山口 智男
広島を拠点にしながら、RED in BLUEはテクニカルでエモーショナルなロック・サウンドとエネルギッシュなライヴを武器に、その名を全国各地に広めてきた。その彼らが全国区の人気に王手をかけるべく、100円という破格の価格でシングル『FRANKEN MUSIC』をリリースする。しかも、ライヴの会場と限定店舗のみの販売だという。単独インタビューとしては本誌初となる今回は、そんな戦略と重心の低いファンク・ロック・ナンバーになった「FRANKEN MUSIC」に込めた狙いや思いについて、バンドのバックグラウンドを振り返りながらメールで尋ねてみた。
-単独インタビューとしては初登場なので、まずはRED in BLUEがどんなバンドなのかというところから教えてください。結成は2012年だそうですね。どんなふうに始まったのでしょうか?
高橋:当時やっていたバンドの解散を機に、僕がぐっち(田口)に電話を掛けたことから始まりました。ぐっちは当時からひと際とがっている先輩だったので、最初は"一緒にやりたい"と言い出せなかったんですけど、"本当はぐっちさんと一緒にやりたいんです!"って泣きながらあとから掛け直してメンバー探しが始まりました。
田口:高橋は高校生のころの対バン相手だったんです。彼は高校を卒業するタイミングだったんですけど、そのころ僕は大学生でぼーっとしてたんですよ。それで、高校時代部活でバンドを組んでいた山崎に声を掛けて。RED in BLUEを立ち上げた当時のベースは磯村ではないんですけど、実はそのころ、すでにmixiで知り合ってセッションをしてました(笑)。
-そのときは、どんなバンドにしたい、どんな音楽をやりたいと考えていましたか?
田口:とにかくメロディが良くて、演奏している僕らも観ているお客さんも刺激的で、面白いものをやりたいと思っていました。初期衝動を大事にしながら、自分の納得のいくメロディを、激しいサウンドでやりたいというのは今も変わらないですね。
高橋:結成当時は、ただ歌うことが好きで、そこに明確なパッションや目標は正直なかったです。漠然と、かっこいいバンドになりたいと考えてましたね。ただ、結成するちょっと前にMY CHEMICAL ROMANCEやSAOSINのような、いわゆるエモ/スクリーモ・バンドに出会って感化されていたので、英詞でシャウトもしてヘヴィな音楽がやれたらいいかも、とは思ってました。当時からぐっちが作る曲は、RED in BLUEの売りでもある歌謡曲を彷彿とさせる和風のメロディだったんですけど、僕の中のエモ/スクリーモ熱もあって、"これをやっていきたい!"とは考えてなかったですね。その後、活動を続けているうちに、ボカロやヴォーカルにオートチューンの掛かったピコリーモが流行り始めて、ぐっちも僕も共通してハマったので、オートチューンをたくさん使った曲やシンセ感が強い曲をライヴでやるようになりました。
-バンド名の由来は?
田口:僕の記憶だと"Red Bull"から取っています。ハイテンションなものやエナジーを連想する言葉として当時マイブームで、愛飲もしていました。でも、高橋はなぜか僕と記憶が違うんですよね(笑)。
高橋:諸説あるんですけど、僕が一番覚えてるのは、THE BLUE HEARTS、RED HOT CHILI PEPPERS、ORANGE RANGE......他にもいろいろいると思うんですが、バンド名に色が入ってたら売れるっていう法則があったので、だったら2色入れちゃえば、2倍売れるんじゃない!? みたいな安易なアイディアから広げていった説です(笑)。
-同期を使わずにリアルタイムなサウンドにこだわるというコンセプトは、結成当初から掲げていたものなのでしょうか?
田口:実は今回のリリース直前から同期を使い始めました。足りないところは気合とエフェクターでカバーするという主義だったのですが、それはバンドマンがバンドマンを意識するゆえの話で、ここ1~2年ぐらいでお客さんが僕らを観ている視点とは少し違うんだなと気づいたんです。CDにはCDの良さがあって、ライヴにはそれとは違った良さがあると思っていたのですが、理想のバランスでギターだったり、コーラスだったりを重ねて録っているんだから、それもライヴで再現したほうがいいんじゃないかと思い始めたんですよ。ライヴでCDのクオリティを超えるものをやるなら、"必要なパートは同期で流すべきだ"という考え方に自然になりましたね。そのうえで、爆裂することがライヴでは大事なんだと。あと、コンピュータやMTRだって楽器なんだと思うようになりました。やってみると目から鱗で、今は楽しくコンピュータでの音楽制作にのめり込んでいます。
高橋:ライヴにこだわるなら、"全部リアルタイムで演奏しないとかっこ良くない!"ってずっと思ってたんですけどね。今もできるかぎりそうするべきだと思っていますが、結局、ライヴで何を一番伝えたいかをシンプルに考えたときに、"曲に込めたメッセージを伝えたい"というところにバンドとして行きついて。だったら、曲が完成する段階で入れたいと思った音――レコーディングで重ねてるギターの音やコーラスを、ライヴで全部伝えきれないのはバンドとしてもったいない。CDはOKで、ライヴは駄目っていうのも矛盾していると思うし、レコーディングして完成させた作品が僕らのメッセージや世界観なら、そのメッセージをより強く叩きつけるのがライヴであるべきだという考えになりました。
山崎:それで可能性が飛躍的に広がるのならとポジティヴな意味で前に進むことを決意しました。
-磯村さんは前ベーシストの脱退後、約2年のサポート期間を経て、今年7月に正式メンバーになりましたが、サポートするようになったきっかけは?
磯村:田口とは、僕が高校生のときに一緒にセッションしたことをきっかけに知り合って、SNSでも繋がってたので、それを通じてRED in BLUEのことを知りました。それからほどなくして、"広島にすごいバンドが出てきた"って噂になってたので、MVをチェックしたり、ライヴに遊びにいったりして。曲もライヴもオリジナリティに富んでいて、かっこいいバンドだなって思ってましたね。サポートするようになったきっかけは、数年ぶりに田口から"焼き鳥屋に行こう"って食事に誘われて、"珍しいこともあるもんだ"って思いながらふたりで楽しくお酒を飲んでたら、帰り際に口説かれました(笑)。僕自身、別のバンドをやっていたこともあって、いろいろ悩んだのですが、最終的にRED in BLUEでライヴをやってみたい! と思いサポートを始めましたね。
-RED in BLUEの音楽はあまりにもユニークすぎて、いい意味でバックグラウンドが見えないのですが、メンバーそれぞれに、どんな音楽を聴いてきたのでしょうか?
田口:僕の音楽的ルーツはアニメ・ソング、パンク・ロック、9mm Parabellum Bullet、ボーカロイドですね。幼少のころからアニメで子育てを受けて、5歳のころには"新世紀エヴァンゲリオン"の「残酷な天使のテーゼ」をフルで歌ってました(笑)。"エヴァ(新世紀エヴァンゲリオン)"は作画と音楽がとにかく素晴らしくて、テープが擦り切れるほどループして見返しましたね。その影響で作画のいいアニメは今でも逐一チェックするほど大のアニメ好きです。中学のときにギターを始めたんですが、それこそFコードが押さえられなくてすぐにやめちゃいました(笑)。それからしばらくして"Mステ(ミュージックステーション)"でザ・クロマニヨンズを観て、THE BLUE HEARTSに辿りついてまたギターに目覚めましたね。シンプルでいて、深い歌詞や音が超かっこ良くて一発で虜になりました。そのころはテクニック主義ではなかったんですが、9mm Parabellum Bulletに出会ってひっくり返されましたね。テクニカルさと初期衝動を見事に両立していて、そのライヴ・スタイルにヒーロー像を見いだして、今でも憧れの対象でいろいろと真似させていただいています。そうして、中学、高校と暗くてどこにも馴染めず、ギターとCDとインターネットが友達だった僕は、音楽が友達のオタク・ギター少年になってました。そんなとき、ニコニコ動画でボーカロイドを知って、そのなんでもありの音楽性に惚れこんでますます捻くれていくんですが、今思えばあの熱量があったから今があるんだと思います。
高橋:高校で初めてバンドを組んだんですけど、先輩の影響でELLEGARDENに出会って死ぬほどハマって聴き狂いました。そこから僕のバンド人生が始まったと思います。また、同じ時期に友達の影響でONE OK ROCKに出会って、Takaさんみたいにかっこいい、鋭い歌を歌えるようになりたくてめちゃめちゃ真似もしてました。そこからMY CHEMICAL ROMANCEやSAOSINを聴き始めたんですけど、高校3年生のあたりで、ふと"自分にとってかっこいい歌ってなんだろう?"と思ってレンタルCDショップでなんとなく目立つ洋楽を借りまくってたら、AEROSMITHに出会ったんです。Steven Tylerの歌に本当に衝撃を受けて、またものすごく真似しました。"こんな声を出せるようになりたい!"って毎日家で布団被って叫んでましたね。そこからBON JOVIとか、GUNS N' ROSESとか同じ80年代のハード・ロックをひと通り聴きました。一番のルーツを挙げるならそのあたりかなと思います。ただ、ジャンルとか時代背景とかは正直あんまり気にしたことがなくて、とにかくこんな歌を歌いたい! っていう感覚で、音というよりは、歌を聴いてきたかなと感じます。コブクロ、秦 基博さん、aikoさんといった日本のポップス・シンガーも好きなんですよ。僕にとってグッとくる歌はなんでも好きです。
磯村:小中学生のころは親の影響でJ-POPが好きで、久保田利伸さんや宇多田ヒカルさんをずっと聴いていました。高校生になって、ジャズ・バンド部に入ったので、その類のジャンルもいろいろ聴いていましたね。特にブラジル音楽が好きでした。同時期に友達の影響でヒップホップもよく聴いてましたね。その中でもGファンクはめちゃくちゃハマりました。
山崎:小さいころからJ-POPが好きだったので、特別バンド・サウンドとか、ドラムがある楽曲を意識して聴いてきたわけではなかったです。ポルノグラフィティ、ORANGE RANGE、大塚 愛さんをめちゃくちゃ聴いてました。楽器を始めた高校生のころからはロック・バンドも聴くようになったんですけど、その中でもバンド問わず、キャッチーな曲を好んで聴いてました。JUDY AND MARYは大好きですね。RED in BLUEをやっていてアレなんですけど(笑)、楽器が出しゃばるよりは、歌がグッとくる曲が僕の音楽人生としてのルーツになっています。
-バイオグラフィを見るかぎり、バンドは着実に活動を進めてきたようですが、ターニング・ポイントになったと言える出来事はありましたか?
高橋:僕の中ではふたつあって、ひとつは2014年のミニ・アルバム『NEW AGE』を作ったときですね。各々の大学卒業のタイミングもあって、バンドとして続けるか迷っていた時期だったので、あの1枚がなければRED in BLUEは今ないかもしれません。デモじゃない初めての作品で、そこで広がった出会いも、バンドを続ける力になったと思います。ふたつ目は、一昨年の1stフル・アルバム『Hybridize』のときですね。制作からレコーディングまで経験したことがないことも多かったので、すごく勉強になりましたし、新曲だけじゃなくて、「ライアーゲーム」、「誰が為」という、これまで共に歩んできた曲の再録もしたし。毎回テーマは何かしらあるんですけど、そのときは、"これがRED in BLUEだ"と言える作品にする必要があったので、これまでで一番RED in BLUEとは何かを考えさせられました。ライヴに対する意識も変わったし、メンバー各々、音楽に対して、自分自身に対しての向き合い方が大きく変わったと思います。
山崎:僕も『NEW AGE』を作ったときだと感じています。CDを持って全国を回るという最初のきっかけになったので。
-活動を続けるなかで目標も変わってきたのではないでしょうか?
高橋:そうですね。結成当初はただ楽しくてやっていただけで、目標を考えたことはなかったんですけど、広島のCLUB QUATTROで"FULL POWER FEST"という自主企画を始めてから、いつか広島で僕たち主催の野外フェスをやりたいというバンドとしての目標ができました。それから、活動を続けるなかで、ただかっこ良くなりたい! っていう気持ちから、具体的にどうかっこ良くなりたいか掘り下げて考えられるようになってきたと思います。
田口:全国区のバンドと対バンする機会もグッと増えてきて、まだまだ上の世界があることを知ると同時に、"全然負けてないのにな"と思うことも増えてきました。こんなにかっこいいことしてるんだから、もっと自分たちは知られるべきだという思いが強いです。今はそのためにSNSだったり、個々の鍛錬だったりで磨きをかけています。これからRED in BLUEのライヴは加速度的に良くなっていくので、ぜひ一度観にきてほしいです。
山崎:ドラマーとしてずっと目標にしてきたところが、ガラッと変わりました。活動を続けるなかでいろいろなバンドと出会い、ドラマーと出会い、そのひとりひとりにストーリーがあって、それをひとつずつインプットして、理想のドラマー像としての視野が広がったと感じますね。"ドラムが一番かっこいい!"という気持ちは、最初の衝動でありながら、最終目標でもあると思うんですが、それはきっと"ドラムがずっと好きなこと"なんだと思います。その目標を変えないために、描いている道のりは変わり続け、吸収し続ける。ただステージ上で色気があるだけのプレイを目指すのではなく、バンドのリズム隊として、まずはメンバーを踊らせることや、ドラムを叩いて、バンド活動を通して何を学んだか、そういうのを全部ひっくるめてドラムに反映できたとき、本当の意味で"ドラムが一番かっこいい"と言える日が来るんだと思います。
-2017年12月に1stフル・アルバム『Hybridize』をリリースしましたが、バンドとしてどんな成果を残せたと考えていますか?
高橋:これまでの僕らとこれからの僕らを掲げて、RED in BLUEというバンドによりしっかり向き合う機会になったので、そういう意味で僕らにとってのスタンダードが生まれた作品になったと思います。ライヴもよりシンプルに進化していきました。バンドとして目指す方向が固まったと思います。
田口:改めて"RED in BLUEとは?"を世間に、そして自分に打ち出せたんじゃないかと。今も自問自答の最中ですが、『Hybridize』はそのときの最適解であり、自分たちのスタンダードを築くことができた作品だと思います。
山崎:初のフル・アルバムということで、リリースまでに費やした時間こそがむしろ成果だと思っていて、本当に今までの比じゃなかったです。収録曲が多いぶん、レコーディングは日数と精神と体力が必要になるし、クリエイティヴな作業なだけに黙々と集中できる日ばかりじゃないし、寝てるとき以外、いや、寝てるときも夢に見ちゃったりするからとにかく考え詰めで。もちろん、これは僕らが成長するにつれて当たり前になることだとは思いますし、どんなことも最初は大変に決まっています。そういった苦労を体験できたという点では、ものすごくありがたいことですね。そういった部分は、乗り越えてきたという自分の自信にもなるし、結果的に音やプレイにも表れてきたと思います。