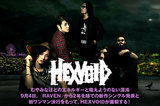INTERVIEW
HEXVOID
2016.08.10UPDATE
2016年08月号掲載
Member:ERC(Vo) 一(Dr)
Interviewer:増田 勇一
-9月4日に下北沢LIVEHOLICでの初ワンマン・ライヴがついに決まりましたね!
ERC:"そろそろやらなくちゃな"という気持ちがずっとあって。もちろん音源のリリースと連動させたいというのもあったんですけど、リリースを待っているうちにどんどん遅れていくのは避けたかったので、まずライヴの日付から先に決めたんです。そもそも俺たち、過去にやってきたUSツアーとかも含めて、できるような状況が整ったらやろうというのではなく、"今すぐできることはとっととやっていこう"というスタンスなんですね。だけどもワンマン・ライヴだけは、ずっとやってこなかった。そこには正直、失敗したくないからというのもあったんですけど、次の段階へ進もうとしている以上、自分たちのやるべき形で一刻も早くそれをやっておくべきだと思えたんで。
一:同時に、お客さんからも"もっと長いセットで観たい!"という声が多かったりして。もちろん対バン形式のライヴをしっかりやっていくことも大事だけど、うちのお客さんはHEXVOIDを起爆剤としながら一緒に盛り上がることを楽しんでくれてるし、そういった人たちを巻き込みながら自分たちなりのノリをしっかりと固めておきたいな、というのがあったんです。HEXVOIDというチームをより確固たるものにしておきたかった、というか。
-ファンのみなさんも、HEXVOIDの長いライヴというのは観たことがないわけですもんね。
一:えぇ。お客さんも対バン・ライヴに慣れているはずだし、そういう場でもウチらならではの色を感じ取ってくれているはずだけど、"もっと楽しめることがあるんだよ"ということを伝えたいなと。それによってお客さん側の欲求も高まっていくことになるんじゃないか、という期待感もあります。それはこちらとしても望んでいることなので。
-自分たち自身としても、ライヴでまだすべてを出し切れていないという消化不良めいた感覚があったわけですか?
一:多少はそういう部分もありますね。
ERC:ただ、ライヴはとにかく激しくやるんで、たとえ30分のセットだろうと、終わったらもう1曲も演奏できないぐらい消耗はするんです。でも、ここ最近のライヴを通じて自分たちの中にすごくいいグルーヴを感じるようになってきていて、しかも後輩世代のバンドもどんどん出てきて......。そんな今だからこそ、俺たちはどんどん先に行って、もっと切り崩していかないといけないんじゃないか、という気持ちが湧いてきたんです。
一:対バンとかイベントとかでのステージって、変な話、全バンドが自己紹介で終わってしまうじゃないですか。"初めまして。気に入ったら今度はうちらのライヴにも来てくださいね"みたいな前提でやっているようなところがある。ところが対バンばかりやっていると、同じような自己紹介を繰り返すことになってしまう。"そういうことばかり続けていてもしょうがないよな"というジレンマも実際あって。HEXVOIDのHEXVOIDらしいところを自分たちとしてももっと感じてもらいたいし、お客さん側もそれを求めてるはずなので。だからワンマンでは、俺たち自身もまだ知らずにいたような意外な部分も出てくるんじゃないかという期待もしています。
ERC:うん。それをやったときに初めて自分たちならではのライヴの形というものが見えてくるようにも思うし、それを経たうえで短いセットで演奏するときには、もっと凝縮感のあるものを披露できるようになるんじゃないかなと思います。というか、そうならないといけないと思う。まずは、ここですべてを出さなきゃいけないというか。
-そして今作『LET IT DIE』のリリースを迎えますが、こちらにもめちゃくちゃ凝縮感があります。
ERC:このシングルについては、ひとまずライヴ会場限定販売で、ワンマン・ライヴの当日から発売になります。
一:Track.1の「LET IT DIE」に関しては"らしさ"のいいとこどりを狙って作ったところがあって。まったく新しいことをやろうとしたわけではないんだけども、このバンドのメロディアスな部分とダンサブルな部分、モッシュが起こせるメタルな部分......そういったおいしいところをすべて総まとめにするような曲にしたいという目論見があったんです。イントロで殺してやろうという気持ちもあったし(笑)。もう1曲の「America」(Track.2)に関しては、そもそも自分たちが得意としてきたヘヴィな縦ノリの曲。昨今、メタルコアにしてもアップビートなものが主流になっていて、そういう曲が少ないじゃないですか。だけどこれが俺たちの色のひとつでもあるし、しかも"テンポが遅いから暴れられない"みたいな感じにはしたくなくて。沸き立てられるようなアグレッションのあるミドル・テンポの曲を作りたいというのが念頭にあったんです。