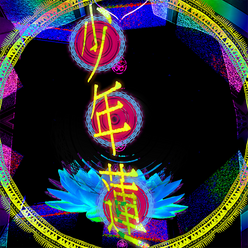INTERVIEW
シェルミィ
2025.09.05UPDATE
2025年09月号掲載
Member:豹(Vo)
Interviewer:杉江 由紀
彷徨える負け犬たちの理論は、たとえ泥沼にはまろうとも這い上がってやるという、不屈の精神に裏打ちされたものなのだろう。"大阪発の負け犬ヴィジュアル系バンド"の肩書きを持ち、自らのファンを"負け犬"と呼称するシェルミィはシングル『少年蓮』でヴォーカリスト、豹の胸中を赤裸々に描くと同時に、現在続行中のツアー"シェルミィ単独見世物公演ツアー「泥」"では、あえての泥臭さを追求しているという。果たして、千秋楽となる12月27日に梅田Shangri-Laにて開催されるワンマン"シェルミィ単独見世物公演ツアー「泥」ツアーファイナル公演「迷い子の理論」"で導き出される結論やいかに?
-最新シングル『少年蓮』のリリース後に始まったツアー"泥(シェルミィ単独見世物公演ツアー「泥」)"で、現在各地を回られているシェルミィですが、来たる12月27日にはそのツアー・ファイナルとしてワンマン・ライヴ"迷い子の理論(シェルミィ単独見世物公演ツアー「泥」ツアーファイナル公演「迷い子の理論」)"を梅田Shangri-Laにて開催されるそうですね。そして、なんと来年にはいよいよ10周年を迎えられるのだとか。
去年くらいまではあんまりそういう実感がなかったし、周りからもまだ若手のイメージで捉えられることが結構あるんですけど(笑)、気付けばもうすぐ10年っていうところまで来てますね。今年に入って一気に"ほんまに俺等、お兄ちゃんになってんねやなぁ"みたいな感覚が生まれてきました。
-シェルミィが始動されたのは2016年5月15日だったそうですが、当時このバンドは何を目指してスタートしたのでしょうか。
ギターの友我とは前身バンドから一緒にやってるんですけど、今のメンバーになってシェルミィとして動き出した当時、自分たちの最も大きい原動力になってたのは"悔しさ"でした。
あの頃の関西っていろんなバンドが活発に動いてて、今はバンド名がΛrlequiΩ表記になってるアルルカンの勢いがとにかくヤバかったし、ヴォーカルの千吊がよく"豹さん、豹さん"って慕ってくれてた後輩のペンタゴンも人気があって、彼等はそのまま関西を出て東京に行ったんですよね。正直なところで"すごいなぁ"という気持ちもありつつ、やっぱり本音の部分では"負けたくない!"って気持ちも大きかったから、そういう劣等感をあえてストレートに言葉にして、シェルミィは"大阪発の負け犬ヴィジュアル系バンド"って肩書きを自分たちに付けて、ファンのことも"負け犬"と呼ぶ形で活動し始めたんです。"見返したい!"っていうちょっとパンク的な精神を持ってメンバーが一致団結したんですよ。
-では、音楽的な面で志していらしたのはどのようなことでしたか。
そこも"見返したい!"の部分と繋がっていて、僕の中では自分が作った曲、自分が書いた歌詞、それを"もっと認めてもらいたい"という気持ちが根底にまずありました。当時は尖りすぎてて、なんなら"認めないやつのほうがおかしい"みたいな感覚で、しばらくやっちゃってましたね(苦笑)。
-今になって振り返ると、それは"若気の至り"だったということだったりして?
まぁ、そのくらい強い気持ちでいたからこそ、劣等感を持ちながらもやれてたっていうのもあるとは思うんですけどね。あと、その頃は"(日本)武道館でやりたい"とか、"みんなが知ってるような大きい事務所から声を掛けられたら嬉しいな"みたいな願望も、あるにはあったものの、バンドを続けていくうちに、だんだんそれより現実的なところに目が向いていくようになりました。自分たちは自主でやってるので、言葉を選ばずに言うとそもそも"ちゃんと食える状態"ではなかったから、純粋にもっと食えるようになりたい=たくさんの動員が欲しいってなったわけです。
-先程のパンク的な精神とも相通ずる、リアルなハングリー精神を持たれるようになったわけですね。
自分の曲とか、自分の歌詞の世界観とか、そういうところにしか向き合ってなかったことに途中で気付いたんですよ。僕が理想ばっかり追いながら、自分がしんどいとか、自分が病んでるとか、ずっと自分の話を曲にしてきた一方で、他のメンバーが現実的なところをいろいろと賄ってくれてたんです。と言っても、最近も自分のことを曲にし続けてるところ自体はあんまり変わってないですけどね。
-最新シングル『少年蓮』に収録されている表題曲や「自分を殺している」、またこれまでに発表されてきている「ファッションマイスリー」(2017年リリースの1stフル・アルバム『ぼくらの残酷激情』収録)、「リストカットベイビー」(2020年リリースの2ndフル・アルバム『平成32年へ。』収録)、「過食性障害嘔吐」(2019年リリースの両A面シングル『過食性障害嘔吐/グルーミーパペットミスフィッツ』収録)といった曲たちも含め、たしかにシェルミィの楽曲は、"病んでいる人"がモチーフになっているケースが多いように見受けられます。メンヘラ少女が主人公になっている場合もある印象ですが、全ては豹さんご自身のことを投映したものだったのですね。
そういうことが結構多いです。それと、自分は私生活で女友達が多いほうだと思うんですね。あ、これは健全な普通の女友達っていう意味ですけど(笑)。きっと、その辺も詞に反映されてるところがあるのかなと思います。
-なるほど。つまり、豹さんはメンタリティ的に女性に近い部分をお持ちなのですね。
そういうところがあるみたいですね。恋愛対象は女性なんですけど、よくメンバーにも"考え方が女子っぽい"っていうことは言われます。自分的には男らしくいたい気持ちもあるんですが、男としての自分と女子っぽい感覚を、両方共作品の中に活かせてるところがあるんだとしたら、それも1つの個性になってるのかもしれません。自分もライヴによく通ってたギャ男やったしね(笑)。
-ジェンダーを問わず、シェルミィの音楽や詞は共感性を呼ぶものになっているということなのでしょう。
実際、そういう人ばっかりじゃないにせよ、うちのライヴに来てくれている人等の中の何パーセントか何十パーセントは、俺みたいな劣等感を抱いてて、そのことで周りが見えなくなっているような人もいると思うんで、共感してくれてる人がいるのは間違いないと思います。
-なんでも、国際比較調査結果によると、欧米諸国に比べ日本人が突出して低いとされているのが自己肯定感なのだそうです。欧米諸国では8割の人が自己肯定感を持っているのに対し、日本人はその半分の4割にとどまるといいます。豹さんの表現されていることは、たくさんの日本人にとって"沁みる"ものなのではないでしょうか。
ここまで9年続けてきて、自分たちに対してもファンに対しても、"さすがに負け犬までは言いすぎやな"って感じてるところは多少あるんですけどね(笑)。でも、これはもともと"必ず下克上を果たして勝ち上がってやる"っていう、前向きな意味を持った言葉なんです。あとは自分を削って仕事をしながらライヴに来てくれる人や、バンドを応援することに人生の重きを置いてる人がいるなかで、ファンの人たちからの共感だけじゃなく、愛を受けて生きてるなっていう感覚が最近はより強くなってきてるんですよ。だから、最近は"どうやったらこのみんなが与えてくれる愛を同じくらい返せるんかな?"って考えることも多いです。
-今回お話をさせていただくまで、シェルミィは、聴き手に救いをもたらすべく音楽を作られているのかな、と想定していたところがあったのですけれど、むしろ豹さんはそれを達成することで、自身も救われたいと願っていらっしゃるのかもしれませんね。そこに至るまでの、言わば"もがき"をシェルミィは音や詞として具現化されているように感じます。
これはたまにMCで話すんですけど、僕は人のことを救いたいっていう気持ちで曲や詞を書いたことはありません。そこは勘違いされたくないところですね。ファンの人たちからは"この曲で救われました。ありがとうございます"みたいなことを手紙やDM、コメントで伝えてもらうことが多くて、もちろんそれはめっちゃ嬉しいし、そういう言葉に支えられてるところも大きいんですけど、自分の心のキャパが限界まで来たときは"なんで、どうして俺は救われないんだ!"って爆発しちゃうこともあるんですよ(苦笑)。ひどいと周りに八つ当たりしちゃうこともあるんで、そんな"誰かのために"なんていう余裕は自分には全然ないです。
-承知いたしました。それから、シェルミィはバンドとしてのコンセプトに、"ぼくらの残酷激情(読み:ボクラノグランギニョル)"という言葉を掲げてもいらっしゃいます。ここにどのような想いを込められているのかも教えてください。
シェルミィの生み出す世界観を分かりやすく伝える言葉が欲しいなと思ったときに、メンバー全員が当時めちゃくちゃハマってた"ライチ☆光クラブ"が、1つのヒントになったというか、"残酷歌劇"を"残酷激情"って形でオマージュしたんです。それもあって、芝居っぽい感じで全員がとある場面で倒れるとか、まさにグランギニョルに寄せた演出をしてたこともありましたね。今でもライヴでは、負け犬たちの飼い主である"犬飼さん"という人物が幕前のナレーションをするって流れを、毎回やってます。
-さて。ここからは最新音源『少年蓮』についてのお話も伺ってまいりましょう。この作品でシェルミィが打ち出したかったのは、どのような面だったのでしょうか。
『少年蓮』に入ってる「少年蓮」に関して言えば、僕の中では作り始めた段階やとかなりネガティヴな曲としてできたものでした。だけど、結果的にはそれを全部逆の意味にして"叶えたくなった"世界みたいにして描いてるのが、この完成形なんです。
この曲ができたきっかけとしては、去年出したフル・アルバム『マイナトランキメズマライザ』に、「バイバイ」と「ラブレットピアス」っていう曲が入ってるんですけど、その曲たちをツアー("シェルミィ 2022年単独見世物公演ツアー 「スプリットタン」")で歌ってたときに、突然歌えなくなってしまったことがあったんですね。そのままステージを下りざるをえなくなったことが1回あって、ある種の挫折感を味わってしまったんですよ。一応その後すぐメンタルクリニックに行って、何種類か薬を貰ったりもしまして、要は自律神経失調症とうつ状態になってたんですけど。
-ともすればイップスに近い状態だったのですかね。
そんな感じやったんだと思います。その頃は曲も作れなくなってたし、いろいろ伸び悩んでる感じもありました。ファンが離れていってるような気もしてて、時期的にはそうなる前にバンド解散の危機みたいなこともあったんで、なんとか立て直そうと頑張ってる感もあったというか。
-バンド解散の危機を乗り越えたところで、そこからの建て直しに必死になるがあまり、心身共に負荷が掛かりすぎていたと。
積み重なっちゃってたんですかね。それでまぁ、1回だけ歌えなくなりつつもツアー・ファイナル("シェルミィ単独見世物公演ツアー「スプリットタン」ツアー最終単独見世物公演「碌デナシ」")を迎えて、そのときにはMCで正直に自分がどうして歌えなくなってしまったのかということや、このツアーをやったからこそ自分は生きることができたんだって話も全てしたんです。で、その後のツアー("シェルミィ単独見世物公演ツアー「アンチテーゼ」")で「ジンテーゼナイフ」(2022年デジタル・リリース)っていう曲をやったときには、その中にも今の自分をリアルに詰め込みました。
-「ジンテーゼナイフ」は"失いたくないから、得ることも臆病なんだ"との歌詞があるだけに、複雑な葛藤を歌ったもののようですね。
何年もやればそのうち売れるとか、どうしても夢見とった自分がいましたからね。何年後にはこうなってるやろうなって思い描いてた理想と、それとは違う全然いろんなことに満足できてない現実があるけど、それでもなんとかもう少し上手く生きていこうみたいな。そんな気持ちを掲げながらやったのが前回のツアー("シェルミィ東名阪単独見世物公演ツアー 「誘発する、デストルド」")やったんですけど、今回の「少年蓮」は"ようやく夢に対して前向きな気持ちで進んで行けるようになれました。ありがとう"っていう曲なんです。話のいきさつが長くなっちゃってすみません(笑)。