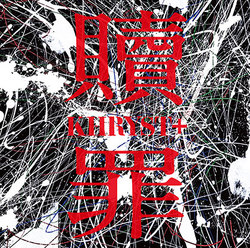INTERVIEW
KHRYST+
2019.05.16UPDATE
2019年05月号掲載
Member:BYO(Vo) QUINA(Gt) IЯU(Ba) JIN(Dr)
Interviewer:藤谷 千明
もうキャリアも関係ないし、いいものは評価される時代ってだけなんです
-「クラクラ」はQUINAさんが原曲を持ってきたとのことで。
QUINA:この曲は、始動ライヴの1曲目にやった曲で、デモの段階でこのタイトルだったんですよね。どうして"クラクラ"だったかというと、このバンドがKHRYST+になる前の仮のバンド名が"Dizzy(めまい)"だったんです。なので、ちょっとラリっている、トチ狂っているようなイメージを持って作った曲です。それで今回BYOちゃんの方から、"このEPに「クラクラ」を入れるのはどうかな?"と相談を受けて。始動当時のものではなく、KHRYST+の活動を経て得たものをアレンジに反映させて、完成させました。
BYO:『BASALT』までは、JINとやりとりして作っていって、それをライヴで発表するという流れでした。それは昔からずっとそうだったんです。でも今回は両A面EPを出すにあたって、"絶対に新しい血を入れたい"、"QUINAの曲を入れるべきだ"という思いが僕の中にあった。始動ライヴでやった曲のままだと、キャッチーさに欠けていたので、サビ次第だから頑張ろうぜと彼に伝えて。
QUINA:この曲って、いい意味でグチャグチャなんですよ。闇みたいな感情、フラストレーション、ストレスを爆発させたような音って、ヴィジュアル系ならではの魅力だと思うんです。少なくとも、僕が中学生のときに、ヴィジュアル系を好きになったきっかけはそこにあった。KHRYST+の活動も、決して順風満帆ではないし、現状の苦しさを音にできたと思っています。昔の僕のような若い子にこの曲を聴いてほしいし、この曲がヴィジュアル系への入り口になってくれたら嬉しいな。
-先ほど、IЯUさんは"この2曲は大変だった"とおっしゃっていましたが。
IЯU:この曲もベースはヤバかったですね。
QUINA:僕の中で、ベースの音のイメージが明確にあったんです。その要望をIЯU君にぶつけちゃったんで、かなりのストレスを抱えていて。
IЯU:締切の2、3日くらい前に"イントロにスラップ入れてくれ"って言われて(笑)。レコーディングが終わったのもギリギリでした。全体的に苦労しましたけど、その結果これまでの自分にはなかった部分も出せて、カッコいいものになったし、苦労した甲斐がありましたね。
QUINA:「クラクラ」はBYOちゃんも苦労したと思う。僕はBYOちゃんのキャラクター性とは別のものを引き出そうとしたんで、最初にBYOちゃんがメロに乗せてきた歌とは、180°くらい変わっているんです。
BYO:「クラクラ」のサビは何パターン作ったんだろう。バチバチでしたね(笑)。
QUINA:(笑)
BYO:結果、お互いが納得いくところに落ち着いたんですけど、本当に人生で一番ギリギリでした。
QUINA:これまでのKHRYST+の音楽制作って、BYOちゃんの持っているヴィジョンを、JINちゃんが曲に起こすというスタイルが主流だったんです。「クラクラ」は、まず僕の意志があるうえで、BYOちゃんの持っているイメージを組み合わせていった......みたいな。これまでにやってきていない方法だったので時間がかかりました。でも、今回これがクリアできたんで、可能性が広がったというか、バンドとしてのレベルが上がったように思います。
-そして"Redemption C"にはライヴでの定番ナンバーと言えそうな「LET'S SING ALONG」が収録されています。
BYO:この曲は、たしかiPhoneでサビのメロディを録音して、JINちゃんに投げてイメージを伝えて作りました。ライヴをもっともっとぐちゃぐちゃにしたい曲ですね!
JIN:歌だけじゃなくて、雰囲気についても具体的に聞いていて。これは生ドラムの音じゃないなと感じたので、ドラムは打ち込みで作っています。
QUINA:僕の中では、この曲はJINちゃんがライヴ中にステージの前方に出てくる曲だと捉えているので、そこを意識しました。
JIN:それは、どういうところなの?
BYO:JINちゃんを引き立たせるためのギター・アレンジですね。実際ライヴでは前に出て、ラップしたり煽ったりしているし。この曲は、珍しくJINちゃんの方から、"こうしたい"みたいな意見もあったんです。今後のライヴのため、曲の知名度を上げるためにも先に出しておきたいなと。
QUINA:ギターが前に出るような曲でもなく、デジタルチックなイメージで作っていきました。
IЯU:この曲に関しては、デモを聴いてすぐにJINちゃんと連絡をとったんです。そこで"いい意味でバンドらしからぬ音にしたい"と聞いて、そこからベースを作っていきました。もっと突き詰めれば、フレーズももっと複雑にすることができたんですけど、歌詞と曲調もわりとストレートなので、ベース・ラインも僕なりの"王道"を作ったつもりです。そしたらJINちゃんが"いいね"って言ってくれて、優しいなって思いました(笑)。
-本作はいわゆる"名刺代わりの1枚"として面白いものになっていると思います。これを持って、今のシーンでどうやって戦っていくのか。先ほどもおっしゃっていましたが、この数年でシーンもかなり変わったというか、頭ひとつ抜けるのが難しいように感じています。
QUINA:それに、かつて突き抜けていた人たちすら、突き抜けられない時代というか。
-それはなぜだと思います?
QUINA:音楽を聴く層って入れ替わっていくものじゃないですか。僕が中学生のときにヴィジュアル系を聴いていた人たちは、今のバンドを聴いていないかもしれない。時代が更新されていくなかで、今はリスナーがヴィジュアル系というジャンルに入っていく"きっかけ"が狭まっているのかもしれないですね。でも僕らはお化粧して、こういう音楽がやりたくてやっているので、今あるシーンに溶け込んでいけたらと思います。
BYO:この数ヶ月活動してきて、溶け込んだ感が全然ないですよね。なんかどんなイベントに出ても......ねぇ?
-とはいえ、そこに迎合するのも違うわけで。
QUINA:周りのものまねをしてもしょうがないんで、僕らのやりたい音楽とお客さんの求めるものが噛み合う瞬間を信じて、音楽を作っていくしかない。
BYO:もうキャリアも関係ないし、いいものは評価される時代ってだけなんです。新たな武器を手に入れて、ようやくバンド的にも戦える状況が作れたと思います。戦っていくのは大変なことだけど、面白くもあり、やりがいはあるでしょうね。