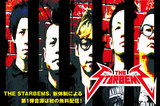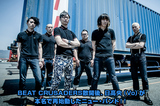INTERVIEW
THE STARBEMS
2014.06.06UPDATE
2014年06月号掲載
Member:日高 央 (Vo) 越川 和磨 (Gt) 寺尾 順平 (Ba) 高地 広明 (Dr)
Interviewer:荒金 良介
-ブログに写真もアップされてましたが、雰囲気のあるスタジオですね。
日高:MELVINSのメンバーのソロとか録ってますからね。理解のあるエンジニアで、いわゆるアメリカのビッグ・サウンドでもなければ、コテコテのどインディーなモコモコの音でもなくて、今の俺らのレベルにちょうど良かったです。
-今回の楽曲の方向性とも合致していた?
日高:ライヴで新曲を試していたけど、この新曲3曲が1番ライヴ映えするし、MANO NEGRAのカヴァーは俺の90年代根性が炸裂しました。何か1つオールド・スクールを入れないと気が済まなくて。今、90年代が俺の中で再び新しくて。クラブやライヴハウスで黙ってFISHBONEの「Party At Ground Zero」とか流したら、反応がいいんですよ。それを俺らなりに伝えたいなと。
越川:MANO NEGRAはどこ行っても言われますもん。
日高:ね?引きはいいよね。特に年輩のニューロティカとか(笑)。ライヴ感のある3曲とカヴァーで今回はバランスはいいんじゃないですかね。4曲だけでライヴしてくれと言われたら、この順番でやろうかなっていう曲順になってるかと。
-なるほど。最初の作品のイメージは?
日高:曲もアメリカ行く前日までリハで詰めていたから、俺らも予想が付かなくて。とりあえずライヴでやってる新曲の中で、いけるものを録ろうと。特にドラムの高地がアレンジをなかなか固めてくれなくて(笑)。
高地:レコーディングしながら変えてましたからね。出発の前日の夜中2時までやってました。
日高:ドタバタでしたね。良くも悪くも詰めてない。
越川:ある種ネイキッドというか。前作はいろんな小細工があったけど、今回はシンプルだし、ライヴでドン!とやっても成立する音数ですね。
日高:一発録りまでいかなくても、それほどオーヴァー・ダブもしてないしね。
越川:せーのでベーシックを録って、少し足しただけです。なので、この6人のライヴ感がきちんとパッケージされたと思います。それは前作と違う部分ですね。前作は録る段階でいろんなものを足して、プリプロとはまた違う曲になることもあったけど、今回は着地点が見えてましたから。
日高:で、録り音はどこに着地してもいいように余裕を持ってね。ほんと録り音は行ってみないとわからないから。日本で録ったらこういう音にならないだろうし、ハイファイ感がないのが逆に良かったと言うか。ローファイじゃないけど、むき出し感がありますからね。最近はそういうバンドも少ない気がして。
越川:エンジニアさんもおおざっぱで"OKOK!"みたいな。エディットするのかと思いきや、何も触らないし。そういう面でもアメリカならではの音源になったと思います。バンドとエンジニアが正面からぶつかった感じですね。
-前作以降に培われたライヴ感で勝負したかった?
日高:もうお化粧しなくていいだろうと。そしたら、ギターのゴスケ(後藤)がお化粧し始めて(笑)。最近、俺の中で80'Sムーブメント再来もあって、SIGUE SIGUE SPUTNIK、THE CUREとかの忘れ去られた80'S感をゴスケに体現してもおうと。何もわかってない奴がコスプレしてる......そこは前のバンドからブレてない気がします(笑)。音楽パロディが好きなんですよね。サウンドはパロディじゃないけど。
-より荒々しいものを求めた理由は?
日高:シンプルに音で伝わらなかったら、伝わらないんだろうなと。アメリカのライヴがまさにそうだったんですけど、俺が元BEAT CRUSADERS、西くんが元毛皮のマリーズとか知らないで、みんな来てるわけじゃないですか。その場でサウンドが良くなければ踊らないし、あっ違うなと思えば目の前を通り過ぎていくし。かと思えば、学生がポゴ・ダンスしてたり、マリファナの臭いもしてくる(笑)。ほんとにカオティックな状態で、音しか問われてないんだろうなという状況があって。そしてそれって世界共通なんですよね。対バンのアメリカ、イギリス、ブラジルのバンドも前歴を知らないわけで、その時に鳴らしてる音しか気にしないから、演者もオーディエンスも。そんな中でブラジルのバンドはアコギにピックアップ付けて無理やり歪ませてて、かっこいいなぁと思って話しかけたら"ゴミ箱で拾ったアコギでやってるんだ"って教えてくれて。そのシンプルさをまざまざと思い出したりなんかもして......バンドを始めた頃はそんな感じですからね。病院の息子さんだろうが、普通のサラリーマンの息子のバンドだろうが、背景を知らずにライヴを観て仲良くなる。だから俺らも余計な説明を省いてもいいのかなと。そのラフさはアメリカでの経験が大きいですね。



















![[MVフル] THE STARBEMS「Vanishing City」](https://i.ytimg.com/vi/8lbgDVxttf0/hqdefault.jpg)